今や、多くの企業では法律や国の方針により、希望すれば再雇用延長で働き続けることができる時代になりました。
しかし、いざ再雇用されたものの、「頼まれる仕事がない」「割り当てられた仕事とやる気にズレがある」といったギャップに直面し、自分の「居場所がない」と感じる方も少なくありません。

再雇用になったけど…誰も何も頼んでこないし、自分はもう必要とされてないのかも

その気持ち、よくわかります 。でも少しだけ視点を変えると あなたにしかできない役割が見えてくるかもしれません
本記事では、そんなモヤモヤや不安を乗り越え、自分らしい役割と働きがい、そして新たな居場所を見つけた8人の実例をご紹介します。
年齢に関係なく、再スタートを切るためのヒントがきっと見つかります。
「孤独感」を突破口に――再雇用で役割を取り戻す第一歩

定年後も働き続けられる制度が整いつつある今、60歳からの再雇用は当たり前になってきました。
しかしその一方で、「やることがない」「誰にも頼られない」と感じ、かつてとのギャップに戸惑い、孤独を抱える人も少なくありません。

昔はあれだけ忙しかったのに 今は誰からも声がかからない

そんな時は 自分の中に眠っている“経験”をもう一度見つめてみましょう 。それが次の一歩のヒントになります
まずは、その気持ちに正面から向き合い、自分なりの役割を見つけていくことが第一歩です。
村田さんもまた、その孤独からの一歩を踏み出しました。
再雇用後の仕事は、資料整理と電話対応だけでした。営業会議には呼ばれず、部下からの相談もなくなり、かつての活躍との落差に、深い孤独を感じていらっしゃいました。
ある日、若手社員が顧客対応で困っている様子を見かけ、「自分の経験が今も役に立つのではないか」とふと思われた村田さん。「任されるのを待つのではなく、自分から動いてみよう」と気持ちを切り替えられたのです。
顧客対応のコツを共有したことがきっかけで、徐々に信頼を取り戻していかれました。「村田さんに聞けば安心」と相談されることが増え、新たな役割と存在感を再び手にされたのです。
【ヒント①】「待つ」より「動く」が、新しい居場所をつくる鍵に
「自分は必要ないのかも…」その不安の正体と向き合うとき

再雇用されたものの、「自分だけが取り残されているのでは」と感じる人は少なくありません。
その背後には、年齢や能力とは別に、制度と実務のズレ、若返り人事、成果主義の浸透といった“構造的な問題”が存在しています。
こうした環境の中でも、自らの役割を見出し、乗り越えた人たちがいます。
次にご紹介するのは、田島さんと佐野さんが直面した現実と、それをどう乗り越えたのかという実例です。
最新設備が導入された部署に配属された田島さんは、これまで得意としていた機械操作や改善のノウハウが通用せず、若手社員との距離も遠く感じ、「自分はいてもいなくても変わらないのではないか」と悩んでいらっしゃいました。
そんなある日、若手社員が機械の不具合に戸惑っている場面に立ち会い、思わず声をかけたところ、田島さんのアドバイスが的確だったことで感謝され、「まだ自分にできることがある」と初めて実感されたのです。
この経験をきっかけに、田島さんはこれまでの知識や経験を整理し、技術ノートとして共有されました。やがて「田島さんに聞けば安心」と言われるようになり、職場での信頼と役割を取り戻されました。
【ヒント②】「通用しない」と感じたときこそ、知識を“見える化”するチャンス
再雇用されたものの、「仕事は特にないけれど、席は用意してある」と伝えられた佐野さんは、日々の業務がほとんどなく、自分の存在意義を見失いかけていらっしゃいました。
そんなある日、若手社員が経理処理でミスをしている場面を目にし、「自分ならこのミスを防げたかもしれない」と気づきました。その瞬間、「与えられないのなら、自分から役割をつくっていこう」と考え方を切り替えられたのです。
ミスを防ぐために、自ら仕組みを設計し、改善案とチェックリストを提案されました。その結果、若手社員のサポート役として周囲から評価され、職場での役割とやりがいを取り戻されたのです。
【ヒント③】「仕事がない」から始まる、新しい“仕組みづくり”の力
「学び直す勇気」が、再雇用後の自分を強くする

かつての実績や経験に頼るだけでは通用しない――それが、再雇用後に多くの人が直面する現実です。
求められるのは、時代に合わせて「今のスキル」を自らアップデートする姿勢。

今さら新しいことなんて覚えられないし 若い人のスピードについていけない

その気持ちは自然なことです 。でも「できる範囲で学ぼう」という姿勢こそが 周囲に信頼される第一歩です
新しい学びに挑戦し、自分の強みを再構築した方々が、職場で再び存在感を発揮しています。
次にご紹介する佐野さんと浜田さんも、そうした変化に向き合い、自ら行動を起こした一人です。
パソコン操作が中心となった業務に戸惑っていた佐々木さんは、若手社員から「スプレッドシートでお願いします」と言われたものの、操作方法がわからず、自信を失ってしまいました。
帰宅後、「もう歳だから仕方ない」と諦めかけた時、「それでも、まだ職場で役に立ちたい」という気持ちが心の中に残っていました。
その思いを大切にし、学び直しを決意されたのです。行動を起こしたことで、未来が変わっていきました。
✅ 乗り越え方:Excel講座を受講し、学び直しを実践
基礎からしっかり学び直した結果、資料作成もスムーズにこなせるようになり、若手社員との連携も格段に向上しました。今では「頼れる先輩」として信頼される存在となっています。
新しい部署に配属された浜田さんは、何をすればよいのか分からず、会議でも発言の機会が与えられない日々が続いていました。かつての経験を活かせないもどかしさから、次第に自己肯定感を失っていかれました。
ある日、「昔、自分は何が得意だったのだろう?」と自問自答する中で、スキルの棚卸しを始めてみたところ、自分の強みと足りない部分がはっきりと見えてきたのです。
これまでの得意分野を再確認しつつ、データ分析や資料作成ツールを新たに学習。こうした努力が実を結び、再び企画メンバーとして抜擢されました。
「待つ姿勢」から「創る行動」へ――再雇用で見つける新たな役割
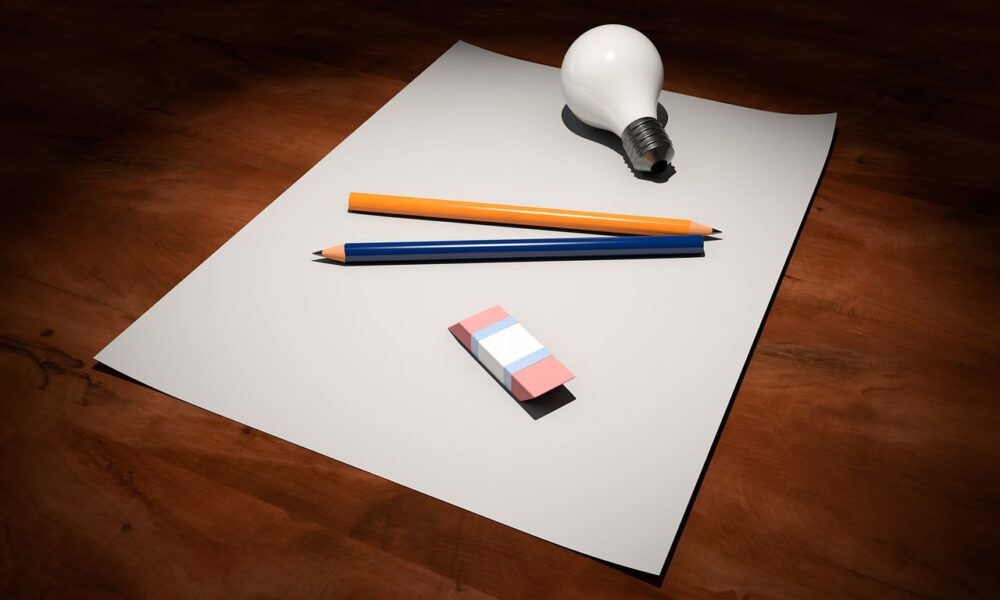
再雇用の現場では、かつてのように指示を待つだけでは存在意義を感じにくい時代になっています。
自分の強みや経験を自ら発信し、役割を創り出すことが求められています。
待つのではなく、動くことで道は開ける――そう実感したのが、三浦さんと岡田さんです。
彼らは、自らの意思と行動によって職場や地域に新たな価値をもたらしました。
再雇用されたものの、実際に与えられる仕事はほとんどなく、「ただ会社にいるだけ」という日々が続いていました。三浦さんは、無力感と寂しさを抱えながら過ごしていらっしゃいました。
そんなある日、新人社員が仕事に悩んでいる姿を見かけ、「自分の経験が役に立つのではないか」と考え、「OJT手引き」を自主的に作成することにしました。「待っているだけでは、何も始まらない」と気づいた瞬間だったのです。
手引きをもとに若手社員の支援を始めたところ、徐々に信頼を集め、研修も継続的に行われるようになりました。肩書きがなくても、“人を育てる存在”として、社内でしっかりと認められるようになったのです。
【事例⑦】岡田さん(63歳・元人事担当)
若手にアドバイスしても「それ、時代遅れ」と返され、かえって距離ができてしまった岡田さん。何をどう伝えればよいか悩んでいました。ある時、逆に若手の話を“黙って聞いてみる”ことに。すると少しずつ打ち解け、「聞いてくれてありがとうございます」と言われたことで、共感の力に気づきました。
相手の立場に立つ姿勢と、時代に合わせた学び直しで信頼を回復。「話しやすい存在」として周囲に受け入れられた。
会社だけが「居場所」じゃない――社会とつながる再スタート
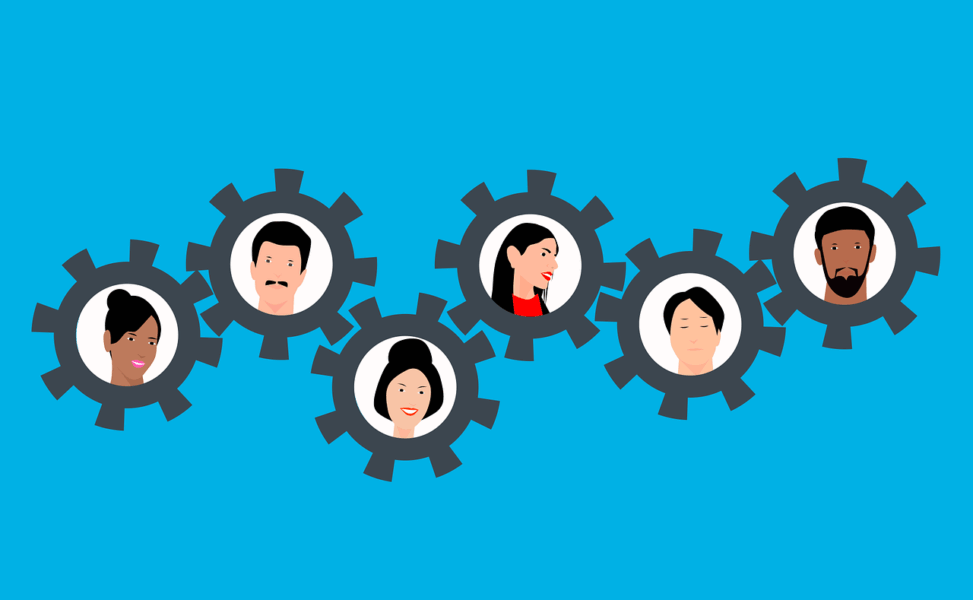
会社の中に活躍の場が見つからなくても、それは「終わり」ではありません。
視野を社外に広げることで、自分の価値や役割を再発見することができます。
地域活動やボランティアなど、社会とのつながりの中で“誰かのために動く”ことが、新たな生きがいや自信につながるのです。
木村さんはその一歩を踏み出し、自分らしい居場所を社外に見つけました。
再雇用後、社内では活躍の場が見つからず、「自分の居場所はもうないのかもしれない」と感じていた木村さん。
そんなとき、地域の掲示板で「子ども食堂ボランティア募集」の張り紙を見かけ、「ここなら自分にも何かできるかもしれない」と思い立ち、参加されました。思い切った一歩が、木村さんの世界を大きく広げることとなったのです。
子どもたちとのふれあいを通して、自分の強みや人とのつながりの大切さを再確認されました。何より、子どもたちの笑顔と「ありがとう」という言葉が、木村さんの自信と喜びにつながったのです。
まとめ:「役割がない」は終わりではない
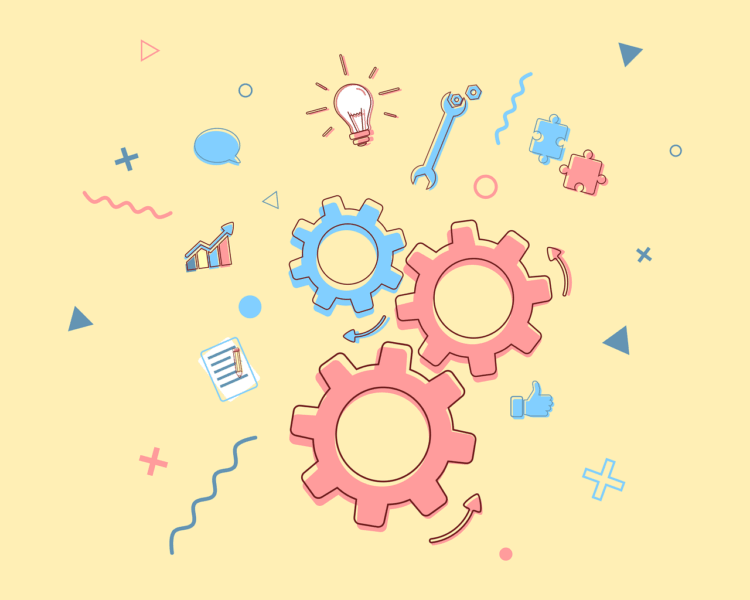
60歳を過ぎて再雇用延長されたものの、「頼まれる仕事がない」「誰からも声をかけられない」と感じ、居場所がないと悩む方は少なくありません。
この記事では、そんな不安や孤独感を抱えながらも、行動によって新しい役割と居場所を見出した8人の実例を紹介しています。
彼らに共通していたのは、「任されるのを待つのではなく、自ら動いたこと」。
たとえば:
- 若手社員に助言会を開いたことで信頼を得た人
- 経験をノートにまとめて共有したことで「聞けば安心」と言われるようになった人
- 新しいスキルを学び直し、再び職場で活躍できるようになった人
- 地域活動に参加し、生きがいを見つけた人
一部の企業では、再雇用延長を断り、転職支援へと切り替える動きも始まっています。
そんな中で、会社が再雇用を延長してくれることは、むしろチャンス。
「居場所がない」と悩むより、「自分に何ができるか」を考え行動することで、会社からも認められるようになります。

誰からも頼まれないし…何をすればいいか本当にわからない

そんな時こそ 目の前の誰かを助けることから始めてみましょう 小さな行動が あなたの新しい役割へとつながっていきます
“与えられる役割”を待つのではなく、“自らつくる役割”こそが、再雇用で輝く鍵です。
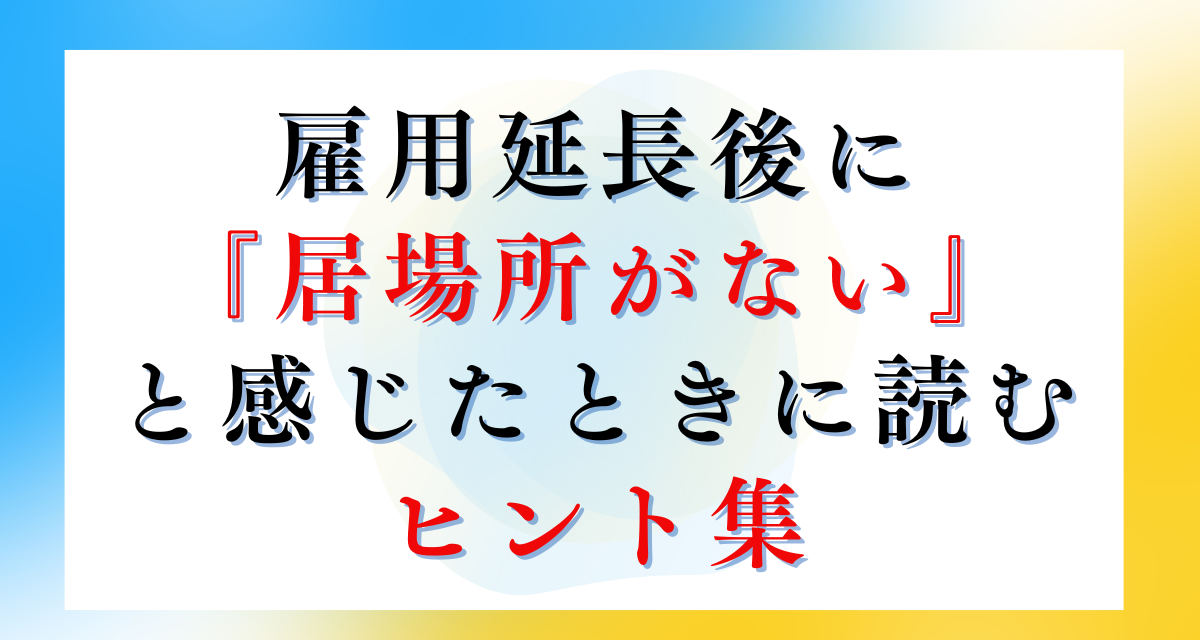
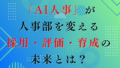
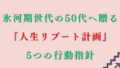
コメント