突然の左遷や降格、望んでいなかった出向、再雇用の打ち切り。
こうした出来事は、誰のキャリアにも起こり得る現実です。
中高年になってキャリアに手応えを感じていたとしても、ある日を境に状況が一変する。
そんな理不尽で避けがたい「働く衝撃体験」を、ここでは「キャリアショック」と呼びます。
病気の発覚で職場を離れざるを得なかったり、希望して選んだ道で降格を受け入れざるを得なかったり、長年培った専門性が突然通用しなくなったり、こうした例は決して特別な話ではありません。
本記事では、実際に私自身や周囲の同僚たちが経験した【実例1】〜【実例5】をもとに、それぞれがどのようにその衝撃を受け止め、どう乗り越えていったのかを丁寧にご紹介しています。
「もし自分だったらどうするだろう?」という視点で、あなた自身のキャリアを考えるきっかけとしてお読みください。
キャリアショックとは

「キャリアショック」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、自分の意思や期待とは無関係に、仕事やキャリアが突如として大きく変わり、心や職業人生に深い衝撃を与える出来事のことを指します。
たとえば、こんな出来事が突然あなたを襲うかもしれません。
- 「難病の発覚で、順調だったキャリアが一瞬で崩れてしまう」
- 「希望して異動した仕事で、まさかの降格を言い渡される」
- 「長年築き上げた専門分野から、まったく未経験の業務へ異動させられる」
- 「信頼されていたはずのポジションを、理不尽な評価で外され、新たな分野に再出発せざるを得なくなる」
- 「働き続けたいという意志とは裏腹に、定年後の再雇用が突然打ち切られる」
こうした現実は、決して他人事ではありません。
これらは、現代の職場で実際に起きている「キャリアショック」の実例なのです。

キャリアショックって、自分にはまだ関係ないと思ってました…

実は、どんな立場の人でも予期せぬタイミングで直面するものなんです。備えとして“知っておく”ことから始めましょう。
以下では、私自身や周囲の人々が実際に経験したキャリアショックのケースをご紹介します。
あなたのキャリアを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
【実例1】突然の病気でキャリアが一変──思い描いていた未来との決別
実は、私自身がキャリアショックを経験しました。
30歳のとき、それは突然やってきました。
ある日、体調に違和感を覚え、病院で検査を受けたところ、難病指定の病気と診断されたのです。
当時、私は仕事も順調で、キャリアに手応えを感じていました。
しかし、病気の影響で松葉杖なしで歩けず、2回の手術を受け、結果として2年間もの長い休職を余儀なくされました。
「仕事を続けたい」という気持ちは強くありましたが、現実はそれを許してくれませんでした。
「キャリアが自分の意志とは無関係に崩れていく」その感覚は、本当に苦しく、無力さを感じました。
どんなに積み重ねてきた努力も、たった一つの出来事で一変してしまうことを痛感した瞬間でした。
その後、私は最終的に元の職場を離れ、地方の関連会社に出向し、最終的には転籍という形でキャリアを続けることになりました。
思い描いていた未来とはまったく違う道を歩むことになりましたが、それもまた一つの再出発だったのです。
【実例2】「希望の仕事」で喜んだはずが…ジョブ型雇用が突きつけた現実
ある日突然、「今まで積み重ねてきたキャリアの価値が変わってしまう」そんな経験、あなたには想像できますか?
これは、私の前職の会社で起きた実話です。
会社全体にジョブ型雇用が導入され、人事部門も例外ではありませんでした。
採用、人材育成、労務管理と、地道にキャリアを積んできた52歳のマネージャーは、「これからはダイバーシティや人権の仕事をしたい」と希望を出し、実際にそのポジションにアサインされてとても喜んでいました。
しかし、その喜びは長くは続きませんでした。
上司からこう告げられたのです。
「君が担当している業務はマネージャーの仕事ではなく、主任クラスのものだ」と。
結果、彼は課長職から主任に降格され、年収も100万円以上減ることになりました。

希望した仕事なのに、降格って納得できない……どう受け止めたらいいんですかね。

やりたい仕事に就けたという『納得感』が、彼にとっては大きな支えになったのです。価値観は人それぞれですからね。
会社側は「ジョブ型雇用は市場価値で判断するものだ」と説明しましたが、彼の心には大きなモヤモヤが残りました。
これまでの実績や経験ではなく、「今まさに担当している仕事の内容」が評価の中心となり、その市場価値によって等級や給料が決まる――それがジョブ型雇用の考え方です。
理屈としては理解していても、いざ自分がその仕組みによって降格や減収を経験する立場になると、そのショックは想像以上に大きなものとなります。
【実例3】人事畑一筋のベテラン管理職が、DX開発部門に突然の異動
私の前職の会社では、50歳のシニアマネージャー(部長級)が人事部に所属し、20年以上にわたり人事の専門家としてキャリアを築いてきました。
しかし、2025年4月からグループ全体の関連会社の人事・総務・経理部門が統合されることになり、彼のポストがなくなってしまいました。
その結果、彼は経済産業省の関連するIT系独立行政法人に出向することとなりました。
新たな職場では、まったく未経験のDX(デジタルトランスフォーメーション)システムの開発業務に携わることになり、人事のスキルは直接活かせない状況です。
出向期間は最長3年とされていますが、その後元の会社に戻れる保証はなく、戻れたとしても元のようなポジションがあるかどうかも不透明です。
これまでの専門性が急に通用しなくなるという点で、まさにキャリアショックの典型例と言えるでしょう。
【実例4】信頼されていたはずのポジションから一転──50歳目前のキャリア転機
「まさか自分が、こんな形でキャリアの方向転換を迫られるなんて」。
そんな思いを抱いたのは、私が50歳を目前にして、事業部のNo.2である部長職に就いていた頃のことです。
あるとき、会社の中でも特に厄介だと評判だった泥沼プロジェクト(長時間間残業が常態化し、赤字と納期遅れが重なった案件)の立て直し要員として、私が「助っ人」として投入されました。
プロジェクトの責任者である事業部長は一切フォローしてくれず、問題が表面化すると、責任のすべてを私に押しつけてきました。
それでも私は、事業部のためにと、事業部長を飛び越えて上位の役員と直接相談しながら、1年かけてそのプロジェクトをなんとか完了させました。
ところが、この行動が事業部長の逆鱗に触れてしまいます。
「あなたを事業部長にするつもりはない。事業部から出ていってくれ」。
それが、私への「評価」でした。
これまでNo.2として事業部の業績向上に尽くしてきたのに、あまりにも非情な仕打ちに、言葉を失いました。
最終的に、上位上司の配慮で人事部へ異動となり、長年築いてきたシステムエンジニアとしてのキャリアは幕を閉じることになりました。
50歳から、まったく異なる分野で新たなキャリアを築く──これもまた、大きなキャリアショックだったのです。
【実例5】「65歳まで働きたい」という願いが叶わなかった再雇用者たち
あなたのまわりにも、「できるだけ長く働きたい」と願う方は少なくないのではないでしょうか。
実際、私の前職のSIer(システムインテグレーター)会社でも、そんな想いを持ったシニア社員がたくさんいらっしゃいました。
しかし2024年から、会社全体で「業務の効率化」と「コスト削減」の両立が強く打ち出されるようになりました。
その中で、特に間接部門(人事・総務・経理、事業部の企画・計画など)に所属し、かつ定年後に再雇用された方々が、「業務上の必然性が低い」と見なされ、真っ先に契約を打ち切られるケースが相次いだのです。
多くの方が「65歳までは働きたい」と考えていたにも関わらず、再雇用の契約を途中で終了され、やむを得ず会社を離れることになってしまいました。
これは、本人の努力や希望とは無関係に起きてしまう、まさに「キャリアショック」と言える現実です。
キャリアショックをどう乗り越えるか!5つの実例から学ぶ「切り替え方」

キャリアショックは、誰にでも起こりうる現実です。
しかし、それをどう乗り越え、どう自分の人生に再び希望を見いだしていくか──そこにこそ、その人らしいキャリアのかたちがあるのかもしれません。
ここでは、実例1~5のそれぞれのケースにおいて、どのように気持ちを切り替え、前を向いたのかをご紹介します。
【実例1の場合】「仕方ない」と受け入れた先に見えた、新たな希望
突然の病気でキャリアが一変し、2年間の休職を余儀なくされた──それは、私自身が体験したキャリアショックでした。
「仕事を続けたい」という気持ちはあっても、体が思うように動かず、もどかしさと無力感に押しつぶされそうになりました。
そんな中で私が選んだのは、「仕方ない」と割り切ること。
会社に迷惑をかけたという気持ちもありましたし、現実を嘆くよりも、今できることに目を向けた方が前向きになれると思ったのです。
また、当時は30歳で、ちょうど子どもが生まれたばかり。
地方の関連会社でも働けることが「ありがたい」と思えたのも、気持ちを切り替える大きな助けになりました。
思い描いていた未来とは違う道ではありましたが、それでも「働けること」「家族を支えられること」に価値を見出すことで、再スタートを切ることができたのです。
【実例2の場合】昔からやりたかった仕事だから─「納得感」が気持ちの支えに
ジョブ型雇用の導入によって、希望していた仕事を任されながらも、まさかの降格と年収減を告げられたこのケース。
52歳という年齢でキャリアの評価が大きく変わることは、確かに衝撃的でした。
しかし、本人がその状況を乗り越えられたのは、「昔からずっとやってみたかった仕事に就けた」という納得感があったからでした。
たとえポジションが下がっても、「本当にやりたいことに取り組める」という実感が、気持ちの支えになったのです。
キャリアとは、必ずしも役職や年収で測られるものではありません。
やりがいや納得感もまた、大切な軸です。
だからこそ彼は、「降格しても仕方ない」と自然に受け入れ、新たな分野で前向きに歩み出すことができたのです。
【実例3の場合】知らない世界を「学び直し」で切り開いた─50代の挑戦
長年、人事一筋でキャリアを積んできたベテラン管理職が、突然まったく未経験のDX開発部門に異動──この変化は、まさにキャリアショックの典型例でした。
しかも、新しい職場では、会議で飛び交う用語すらわからない状態からのスタートだったのです。
そんな彼がこのショックを乗り越えるために選んだのは、「学び直し」でした。
まず、基礎的なIT知識を身につけるためにITパスポート試験に挑戦。
さらに、AIやディープラーニングについて体系的に理解するために、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)のG検定(ジェネラリスト検定)を受験し、半年間でこれらを見事に取得しました。
「知らないことは、学べばいい」──そう割り切って、自分自身の知識の幅を広げる努力を続けた結果、彼は徐々に新しい仕事にも手応えを感じるようになっていったのです。

50代から全く別の分野に挑戦なんて、無謀じゃないですか?

“知らないことは学べばいい”という姿勢が、キャリアの再構築につながりました。年齢は壁ではないということはしっかり理解しましょうね。
年齢や専門分野に関係なく、変化を受け入れて学び直すこと。それが、キャリアショックを乗り越える強力な武器になるという好例です。
【実例4の場合】「50歳、まだやれる」─経験を活かして新天地で信頼を築いた私の実例
これは、私自身の実例です。
長年勤めた事業部で、No.2のポジションとしてプロジェクトを支えていた私。
しかし、泥沼化したプロジェクトの立て直しを任されたことで、評価どころか逆に事業部長の怒りを買い、「事業部から出ていってくれ」と告げられるという想像もしていなかった結末を迎えました。
正直、悔しさもありましたが、「まだ50歳。ここからが勝負だ」と自分に言い聞かせ、新天地の人事部で新たなスタートを切る決意をしました。
そのときに私が頼りにしたのは、かつてSEとして現場で奮闘していたときの経験です。
特に、長時間残業をどう減らすかという現場での苦労は、私にしかわからないリアルな課題でした。
その経験を活かし、残業マネジメントシステムの企画・開発・運用を任され、全社的な長時間労働の是正に貢献することができたのです。
その結果、私は「現場のわかる労務管理のエキスパート」として人事部内で新たな立ち位置を得ることができました。
システムエンジニアとしてのキャリアは終わりましたが、そこで得た経験は決して無駄ではなかった。キャリアの終わりと思えた出来事が、新たな道の入り口だったのです。
【実例5の場合】「このあたりで、会社人生を終わりにしてもいいか」──失望の中に見えた静かな決断
これは、私の前職の同僚である63歳の再雇用社員の実例です。
彼は「65歳までは働きたい」と願っていました。
体力も気力もあり、まだ会社に貢献できるという自負もあったそうです。
しかし、2024年から始まったジョブ型雇用の全面採用、そして人事・総務・経理などの間接部門の統合によって、再雇用者への風当たりが急に強くなり、ついには契約終了を告げられました。
そのとき、彼は強いショックを受けました。
けれども同時に、「稼げない社員はいらない」と言わんばかりの会社の変化に、深い失望と違和感を抱いたとも語っていました。
そして、「もういいかな」と、静かに思うようになったそうです。
60歳を過ぎ、会社が変わっていく様子を目の当たりにして、長年頑張ってきた自分の会社人生に区切りをつけるべき時期だと、自然に思えるようになった──それが彼なりの乗り越え方でした。
キャリアショックを無理に跳ね返そうとするのではなく、状況を受け入れ、次の人生を考える。そんな静かな切り替え方もまた、ひとつの「成熟した決断」と言えるのかもしれません。

努力しても報われないなら、働く意味ってなんだろう…

状況を受け入れ、“今をどう生きるか”を考える姿勢もまた、成熟した選択になるのです。
まとめ

キャリアショックは、突然訪れ、心を大きく揺さぶる出来事です。
しかし、それは「終わり」ではありません。むしろ、そこから「どう切り替えるか」によって、その後の人生が大きく変わってくるのです。
本稿で紹介した5つの実例は、それぞれ異なる背景や状況のもとでキャリアショックに直面し、次のような切り替え方を選び取りました。
実例1(病気でキャリアが一変)→「仕方ないと割り切る」。理不尽ともいえる現実を受け入れ、自分にできることに集中する姿勢が、新たな再出発の道を開きました。
実例5(再雇用打ち切り)→「受け入れて区切りをつける」。望んでいた継続就業が叶わなかった現実を静かに受け入れ、「ここで終わりでもいい」と自然なかたちで次の人生へ歩み出しました。

自分が同じ立場になったら、どんなふうに乗り越えられるだろう…?

自分なりの『切り替え方』を考えることが、キャリアの不安を力に変える第一歩になると思いますよ。
このように、キャリアショックに直面したときの「切り替え方」は一つではありません。
「割り切る」「納得する」「学び直す」「経験を活かす」「受け入れる」――それぞれが、自分自身の感情と向き合いながら、未来への希望を見出していったのです。
大切なのは、自分の感情を否定せず、その時の状況に応じて「できる一歩」を踏み出すこと。
年齢や立場に関係なく、柔軟に自分のキャリアを見直す力が、これからの不確実な時代を生き抜く大きな武器になるのです。
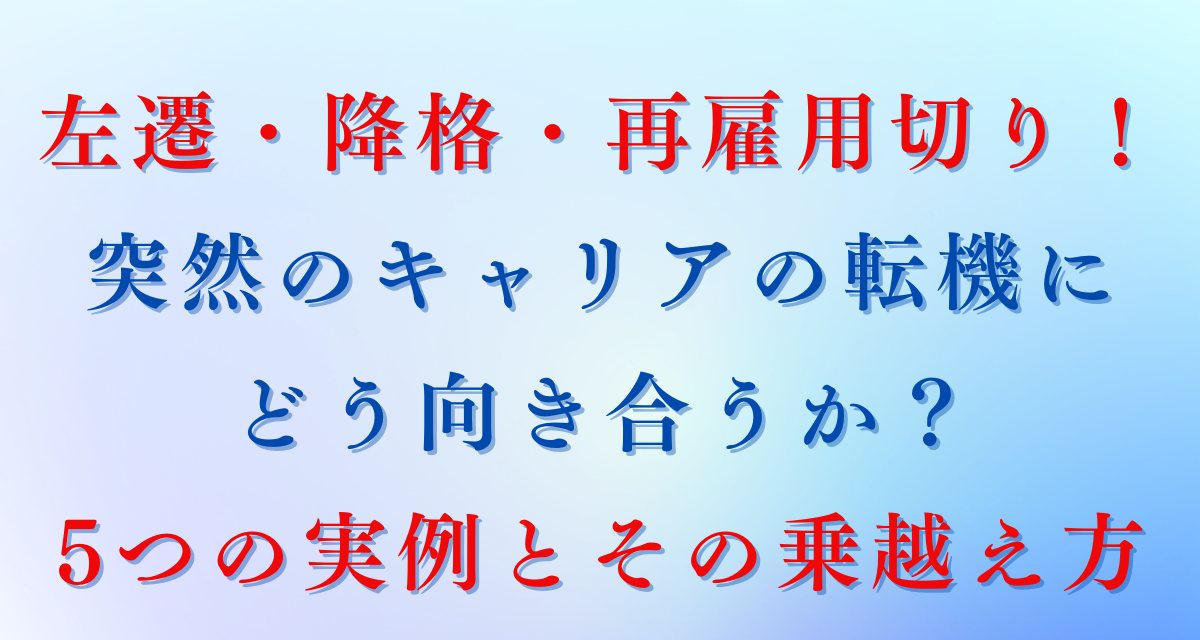
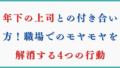

コメント