坂本竜馬は、高知県(旧土佐藩)の郷土の英雄として愛され、その生涯は多くの高知県民にとって特別な存在です。
その人気は、鹿児島(旧薩摩藩)の西郷隆盛が地元で絶大な支持を受けるのと同様、現在でも変わることはありません。
司馬遼太郎の「竜馬がゆく」は、そんな坂本竜馬の人生を鮮やかに描き出した長編小説で、歴史を超えたエンターテインメントとして評価されています。
この小説には、幕末という激動の時代を生き抜いた竜馬の姿が、自由奔放で革新的な視点から描かれています。
また、史実と創作が巧みに織り交ぜられた司馬史観によって、竜馬という人物がより魅力的に立体的に書かれています。
郷土の英雄としての竜馬の活躍はもちろん、彼を取り巻く志士たちとの交流や、彼自身の内面を描いた場面も見どころです。
特に「寺田屋事件」や「船中八策」、そして「新婚旅行」など、ドラマや映画でも取り上げられるエピソードは、歴史小説としての枠を超えて多くの読者の心をつかんでくれます。
「竜馬がゆく」のあらすじ

坂本竜馬の生涯を描く「竜馬がゆく」は、幕末という激動の時代を駆け抜けた彼の成長と活躍を追った壮大な物語です。
ここでは、彼の人生を彩る重要なエピソードをわかりやすくご紹介します。
竜馬、黒船に衝撃を受ける若き修行者
19歳の坂本竜馬は、剣術修行のため故郷の土佐を離れ、江戸へ旅立ちます。
その直後、ペリー率いる黒船が来航し、竜馬は異国の力を目の当たりにして強い衝撃を受けます。
この体験が、彼の中に時代の変化を意識させ、大志を抱く契機となります。
武士としての枠を超え、新しい日本の姿を模索し始める竜馬の旅路がここから始まります。
土佐を去る決意と尊王思想の目覚め
土佐勤王党に加入した竜馬は、尊王攘夷思想に触れながら志士たちとの交流を深めます。
中でも、長州藩の久坂玄瑞との出会いは彼の思想を大きく変化させました。
理想を追い求める中で土佐藩の閉鎖的な体制に限界を感じ、脱藩を決意。幕末という激動の舞台に立つため、新たな道を切り開きます。
勝海舟との出会いが変えた運命
脱藩後、竜馬は幕府海軍の指導者・勝海舟と出会います。
この出会いをきっかけに、攘夷思想から開国論へと思想を大きく転換。
勝の指導を受けた竜馬は、理想だけでなく現実を見据えた実践的な行動力を身に付け、幕末の表舞台で活躍するための基盤を築いていきます。
薩長同盟成立への立役者
竜馬は勝海舟の片腕として、幕末の混乱を調停する役割を果たします。
特に薩摩藩と長州藩の仲介に尽力し、薩長同盟の成立に大きく貢献しました。
この同盟が倒幕への道筋を作り、幕末の行方を大きく変える結果となります。
竜馬の存在は、志士たちを繋ぐ重要な架け橋となります。
未来を見据えた「船中八策」
竜馬は、日本が進むべき未来を「船中八策」としてまとめました。
そこには、大政奉還や議会政治の導入、憲法の制定、開国などが含まれており、後の明治政府の政策に大きな影響を与えます。
時代を先取りする構想力で、新しい日本の形を描き出した竜馬の思想は、現代にも通じる普遍的な価値を示してくれます。
志半ばで散る幕末の英雄
1867年、竜馬の念願であった大政奉還が実現し、幕末の歴史は大きく動きます。
しかし、そのわずか1か月後、竜馬は京都の近江屋で何者かに暗殺され、31歳という短い生涯を閉じました。
志を抱き続け、時代を切り開こうとした竜馬の生き様は、多くの人々の心に深い感動を与えています。
この本はこちらで購入できます。
司馬史観を超えた魅力!「竜馬がゆく」の世界

司馬遼太郎の「竜馬がゆく」は、坂本竜馬の魅力を存分に描いた小説です。
司馬史観や名前の表記など、創作の背景を知ることで、さらに作品の奥深さを楽しむことができます。
司馬史観を知っても「竜馬がゆく」を好きな理由
私が司馬遼太郎の「竜馬がゆく」を好きな理由は、坂本竜馬という人物の自由闊達で革新的な生き様に深く共感するからです。
低い身分から大局観を持ち、幕末という激動の時代を切り開いていく姿は、勇気と希望を与えてくれ、ワクワクします。
また、天真爛漫な性格や誰にでも分け隔てなく接する人間性も魅力的です。
さらに、司馬遼太郎の文章は読みやすく、土佐弁を駆使した生き生きとしたセリフやユーモラスな描写が、歴史小説を堅苦しく感じさせません。
司馬史観により「船中八策」や「薩長同盟」などの史実と違うと言われていることは知っています。
ただ、その巧みな筆力で描かれる物語の魅力は揺るぎません。
「竜馬がゆく」は、史実を超えた創作の力で歴史の面白さと人間の可能性を教えてくれる、私にとって特別な作品です。
なぜ司馬遼太郎は「龍馬」でなく「竜馬」を選んだのか
私の推測ですが、司馬遼太郎が「龍馬」ではなく「竜馬」という表記を選んだ理由には、小説家としての創作の自由を確保する意味があったと思われます。
司馬遼太郎は、史実の坂本龍馬ではなく、自身の解釈で生み出した自由な人物像を描くため、「竜馬」と表記することでフィクション性を強調したかったのではないでしょうか。
この作品は、史実と創作が絶妙に融合した魅力的な歴史小説です。
「竜馬がゆく」を通じて、幕末の激動と竜馬の生き様に触れてみてはいかがでしょうか。
この本はこちらで購入できます。
「竜馬がゆく」の魅力を深める逸話たち

「竜馬がゆく」には、坂本竜馬の波乱に満ちた人生が多くのエピソードとともに描かれています。
ここではあらすじに登場した重要なエピソード以外にも、彼の人物像を立体的にする理解できる興味深い逸話をご紹介します。
寺田屋事件(1866年)
寺田屋事件は、坂本竜馬の人生を語る上で欠かせない、ドラマでもしばしば取り上げられるエピソードです。
京都の寺田屋に滞在中、幕府役人の襲撃を受けた竜馬は、命がけの危機に直面します。
しかし、同じ宿にいたお龍(のちの妻)の機転によって九死に一生を得ました。
新婚旅行(1866年)見出し3
坂本竜馬とお龍の新婚旅行は、日本初の新婚旅行とも言われ、多くの人々の関心を集めるエピソードです。
寺田屋事件での負傷を癒すため、2人は現在の霧島温泉郷を訪れました。
この旅行は、激動の時代を生きた竜馬の私生活を垣間見せる貴重な場面として、ドラマや小説でしばしば描かれています。
大政奉還(1867年)
大政奉還は、1867年に坂本竜馬が徳川慶喜に提案した政治改革案です。
竜馬は、幕府が政権を朝廷に返上し、新たな政権を樹立することで、内戦を避けつつ平和的に新しい日本を作る道を模索しました。
この提案により、江戸幕府は約260年の歴史に幕を閉じることになりました。
これらの逸話は、「竜馬がゆく」をさらに魅力的にする要素の一部に過ぎません。
坂本竜馬の生涯を彩る多くのエピソードを通じて、彼の人間性や志に触れることができるのも、この作品の大きな魅力です。
この本はこちらで購入できます。
坂本竜馬の名言集

坂本竜馬の名言は、私にとって生きる指針であり、働く上での心の支えとなりました。
彼の言葉は、困難に直面したときや道に迷ったとき、自分の信念を貫き、柔軟に対応する力を与えてくれました。
竜馬の先見性や行動力に励まされ、常に新しい視点で物事を捉え、成長を続ける勇気を持てました。
「世の人は我を何とも言わば言え、我が成すことは我のみぞ知る」
この名言は、坂本竜馬が自分の信念を貫く強い意志を表しています。
他人の評価や批判に惑わされず、自分が信じる道を進むという覚悟を示しています。
竜馬は時代の変革者として、多くの批判や誤解を受けながらも、理想に向かって突き進んでいました。
「日本を今一度せんたくいたし申候」
この言葉は、坂本竜馬が日本を刷新し、古い体制を一掃する必要があると考えていたことを示しています。
「せんたく」とは、国を清め、改革することを意味します。
幕末の混乱を目の当たりにし、竜馬は新しい時代を切り開くために根本的な変革が必要だと感じていました。
「人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある」
竜馬はこの言葉で、多様な考え方やアプローチを尊重する姿勢を示しています。
彼は、決して一つの道に固執せず、状況に応じて最適な選択をする柔軟性を持っていました。
これは、薩長同盟や大政奉還といった複雑な交渉を成功させた要因の一つです。
まとめ

「竜馬がゆく」は、司馬遼太郎の独自の視点で描かれた創作要素も多く含む作品です。
そのため、司馬史観が信用できないと批判する人もいるかもしれません。
しかし、この小説は歴史の枠を超え、圧倒的な面白さと娯楽性を持つ傑作です。
坂本竜馬の自由闊達な人間性や、命を懸けて時代を切り開こうとした姿勢は、私たちに勇気と希望を与えてくれます。
また、読みやすい文体やユーモラスなセリフは、歴史を身近に感じさせてくれる魅力の一つです。
史実だけでは伝えきれない竜馬の人間的な魅力を存分に味わえるこの作品を、ぜひ多くの人に手に取っていただきたいと思います。
この本はこちらで購入できます。
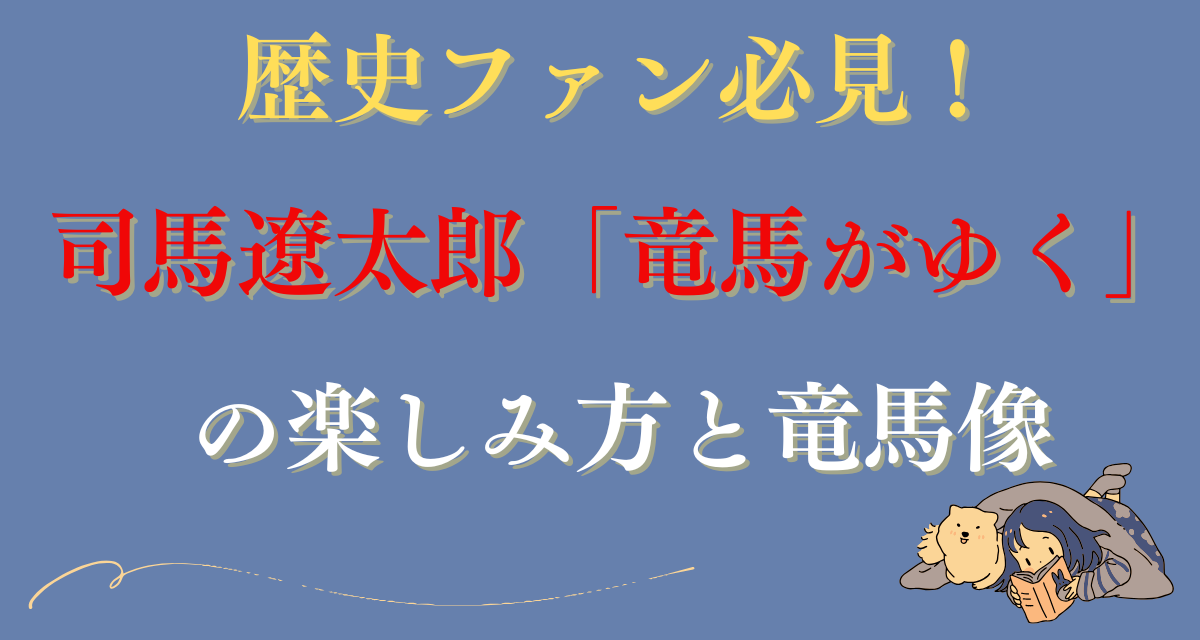
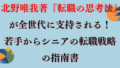
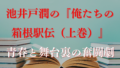
コメント