大企業においては今、人事・総務・経理といった間接部門の業務を、本社がグループ会社を横断して一括で支援・管理しようという動きが加速しています。
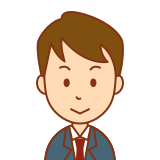
本社集約やAI活用って言われるけど人事の仕事はどう変わるのか正直不安です

その不安はとても自然です。だからこそ今 人事の役割を整理して考える価値があります
その背景には、「生産性向上」という強い目的と、それを支える生成AIの進化があります。
こうした全社的な業務集約は、AIの活用なしには実現できません。
とくに人事領域では、採用・評価・育成といったあらゆる業務で、AIが膨大な人材データを分析し、客観的かつスピーディに意思決定を支援するようになってきました。
しかし、AIができるのはあくまで「整理」と「予測」。
社員の本音を汲み取ったり、成長を支える関係性を築くのは、やはり人間の役割です。
本記事では、生成AI時代において、人事部門がどのような役割を担い、どう本社と現場で支え合うのかを、具体例を交えて考えていきます。
生成AIが拓く、グループ採用の新しいカタチ

これまで多くの企業では、グループ各社ごとに採用担当者を置き、それぞれの組織文化や業務特性に応じた人材採用を行ってきました。
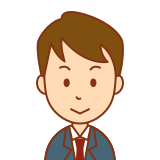
本社一括採用って 現場の声が置き去りにならないか心配です

だからこそ AIと人が役割分担する設計が重要になります
しかし近年、生成AIの進化により、採用業務の“見える化”と“標準化”が一気に進展。
グループ全体での採用を本社主導で効率的に管理する仕組みが、現実のものとなりつつあります。
AIが応募者のスキルや志向性を分析し、適性の高い人材を短時間で推薦できるようになった今、グループ採用のあり方そのものが変わろうとしています。
では、このようなAIを活用した採用体制において、人間は何を担うべきなのでしょうか?
本社と現場の役割分担を再考する時が来ています。
AIによる精密スクリーニングが可能にする「最初の見極め」
生成AIは、履歴書やエントリーシートの文面を自然言語処理で解析し、応募者の志向性やポテンシャルをスコア化することが可能です。
これにより、数百人〜数千人に及ぶ応募者の中から、一定の基準を満たす候補者を短時間でスクリーニングでき、人事部の初期選考の工数を大幅に削減できます。
さらに、過去に採用した人材の職種別・部署別の活躍データをもとにAIに学習させることで、「この部署ではこういうタイプの人が成果を出しやすい」といった傾向を抽出することが可能になります。
たとえば、SE中心の部署では論理的思考や要件定義の経験が重視され、ネットワーク系ではトラブル対応力や認証技術の知識が評価されるといった違いです。
このように、部署や業務内容に応じた“マッチング精度の高い人材像”をAIが学習・判断することで、より的確な候補者推薦が可能となります。
ただし、その精度を高めるには、現場との連携と継続的なデータ更新が不可欠です。
カルチャーフィットはAIでは測れない——人事の対話力が鍵に
一方で、どれだけAIが精密なスコアを出しても、「一緒に働きたいか」「現場になじむか」といった職場との相性までは完全に分析しきれません。
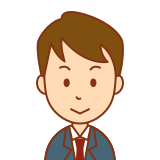
AIがあるなら 人事の経験や勘はもう不要なのではないですか

人の想いや価値観を引き出す力はこれからも人事にしかできません
特に中途採用や管理職採用では、業務スキルだけでなく、「会社の価値観と候補者の考え方が一致しているか」や、「チームをどう巻き込むタイプのリーダーなのか」といった“組織との相性”が、定着や成果に大きな影響を与えます。
たとえば、「上から指示するタイプのリーダー」よりも「現場の声を聴きながらチームを導くスタイル」の方がフィットする文化の企業では、そのスタイルの違いが採用の成否を分けることもあります。
こうした微妙なニュアンスを見極めるためには、人事担当者が面接での会話を通じて、候補者の価値観や仕事観を丁寧に引き出し、現場の空気感や企業文化との整合性を見極める必要があります。
単なる履歴書の情報ではわからない「人間的な相性」を見抜くための“対話力”と“洞察力”が、これからの人事に欠かせない力なのです。
一括採用の落とし穴——“現場感覚”をいかに反映させるか
本社一括による採用では、選考プロセスの標準化によって公平性が高まり、全体のスピードも格段に向上します。
しかしその一方で、各現場が持つ独自の“肌感覚”——たとえば、「この職場ではコミュニケーションが得意な人が長く活躍している」「地方拠点では地元志向の人材の方が定着しやすい」といった暗黙知——を見落としてしまうリスクがあります。
特に地域や職場文化が異なるグループ会社では、求める人材像も微妙に異なります。
例えば、東京本社ではスピード重視の人材が求められていても、地方の開発拠点では粘り強く現場に寄り添えるタイプの人材が好まれることもあるでしょう。
AIは過去データから傾向を分析できますが、こうした“現場ならでは”の人材像までは自動で判断することは困難です。
そのため、本社と現場との密な連携が不可欠です。
現場の採用担当者やマネージャーが「どんな人材がチームにフィットするのか」を定期的にフィードバックし、その情報をAIの選考モデルに反映させることが必要です。
つまり、AIの「学習素材」は、現場の声によって育てていくものであり、それを怠ればいくら高性能なAIでも“現場ズレ”を起こしてしまうのです。
評価制度の再構築—定量+定性の“ハイブリッド型”へ

生成AIの導入によって、評価においても“客観性”と“スピード”が求められるようになっています。
KPIや業務成果をAIが自動的に分析し、数値としてフィードバックすることで、上司の主観や感情による偏りを減らすことが可能です。
しかし、その一方で、「数字では測れない努力」や「チームへの貢献」といった定性的な評価は、ますます人間に求められるスキルとなります。
評価制度の再構築においても、“AIにできること”と“人間にしかできないこと”の切り分けが問われています。
AIによる評価の自動化と公平性の確保
ジョブ型雇用の広がりにより、業務ごとの成果が明確に定義され、KPIや勤怠データのような“定量データ”に基づく評価がしやすくなりました。
AIはこれらのデータをリアルタイムで処理し、標準化された評価レポートを自動で出力します。
これにより、属人的な評価からの脱却と、社員への透明性の高い説明が可能になります。
現場マネージャーの「文脈力」が問われる時代
数字だけでは見えてこない背景——たとえば、プロジェクトの難易度の違いや、チームメンバーの途中離脱、予期せぬ業務変更など——を読み取る力が、現場マネージャーには求められます。
たとえば、ある社員の成果スコアがAIの分析で「平均以下」と出たとしても、その理由が「プロジェクト開始直後に主要メンバーが抜け、一人で複数業務をこなしていた」などの事情によるものであれば、単純に低評価とは言えません。
このように、AIの出す評価結果が「なぜその数値になったのか」を人間が説明できなければ、現場も本人も納得できる評価とはなりません。
だからこそ、評価者には「対話力」と「背景理解力」が、これまで以上に求められるのです。
AIによる評価は“道具”であり“答え”ではない
AIが出力する評価スコアやパフォーマンス分析は、あくまで「考えるための材料」にすぎません。
たとえば、AIが「この社員は売上実績が低い」と判定しても、その背景に「新規顧客が少ないエリアを担当していた」「社内調整が多く、顧客対応の時間が限られていた」などの事情があれば、数字だけで判断するのは不適切です。
大切なのは、AIの出す数値を「そのまま評価の答え」として受け取るのではなく、「なぜこの数値になったのか?」を人間が深掘りし、本人との対話を通じて課題や強みを明確にしていくことです。
つまり、AIによる評価は、あくまで“道具”。
評価の本質は、データをもとにどう向き合い、どう成長を支援するかという、人と人との関わりにあります。
育成とキャリア支援—個別最適化の新常識

これまでの企業研修は、年次や職位に応じて全社員に同じ内容を提供する“一律型”が一般的でした。
しかし生成AIの導入により、社員一人ひとりのスキルレベル、業務履歴、志向性に合わせた“パーソナライズ育成”が現実のものとなりつつあります。
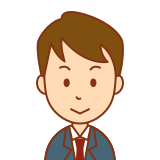
AIで育成まで管理されたら人と向き合う時間が減るのではないですか

AIがあるからこそ人と向き合う時間を増やせます
たとえば、AIが「過去にデータ分析プロジェクトで成果を出した社員」を検出し、その社員に高度なデータ分析講座を推薦する、といった個別最適化が可能になります。
さらに、本社がグループ全体の人材データを統合・分析できるようになることで、各グループ会社に分散していた研修や育成リソースを効率的に共有・展開できるようになります。
これにより、地方拠点や小規模部門の社員も、これまでアクセスが難しかった高度研修や成長機会を得られるようになるのです。
このように、AIは育成を効率化する“道具”として活用され、人間はその結果を見ながら最適な支援策を判断する——そんな役割分担が、今後ますます重要になります。
AIが導く「成長ロードマップ」の可視化
AIは社員一人ひとりの過去の業務実績、取得スキル、社内での評価コメントなどを横断的に分析し、「この人には次にどんなスキルが必要か」「どの部門でより活躍できそうか」といった“成長の道筋”を提示できます。
たとえば、営業部門で成果を上げた社員が「分析力」や「市場理解」の強みを持っていれば、AIはマーケティング職への適性を判断し、必要な研修やスキル習得ステップを具体的に提示します。
従来は上司の経験や感覚に頼っていたキャリア支援も、AIの活用で客観的な根拠に基づいた“見える化”が進みます。
社員自身が、これまでの実績と将来像を照らし合わせながら、自分に合ったキャリアを「自分の言葉」で描けるようになるのです。
人事担当者の“共感支援”がカギを握る
AIによるキャリア提案がどれほど精密でも、それを“本人がどう受け止めるか”は別問題です。
たとえば、AIが「マネジメント適性あり」と提案しても、本人は「まだ現場で技術を極めたい」と思っているかもしれません。
こうした“本音”を引き出すのは、面談や日々の対話を通じた人事担当者の共感力です。
AIの提案を一方的に押し付けるのではなく、「このキャリア提案を、どう思いますか?」「あなたが今やりたいことは?」と丁寧にすり合わせる姿勢が求められます。
人事が“伴走者”として寄り添うことで、社員は安心して自分の成長に向き合えるようになります。
「育成」は企業文化を伝える機会
社員育成の場は、単なるスキル習得のためだけではありません。
そこには、「この会社で大切にしている価値観」や「チームとしてどう動くべきか」といった企業文化を伝える役割もあります。
たとえば、オンライン研修やeラーニングを受けるだけでは、会社が大切にしている“フィードバックの文化”や“チームの空気感”はなかなか伝わりません。
だからこそ、研修後に上司や先輩が1対1で対話し、実務への活かし方をフィードバックする機会を設けたり、社内メンター制度を組み合わせたりといった、人との関係性を前提とした設計が重要です。
こうした設計は、AIには担えない、人事だからこそできる仕事です。
育成の場を通じて「この会社で働く意味」を感じさせることが、定着と成長につながるのです。
まとめ
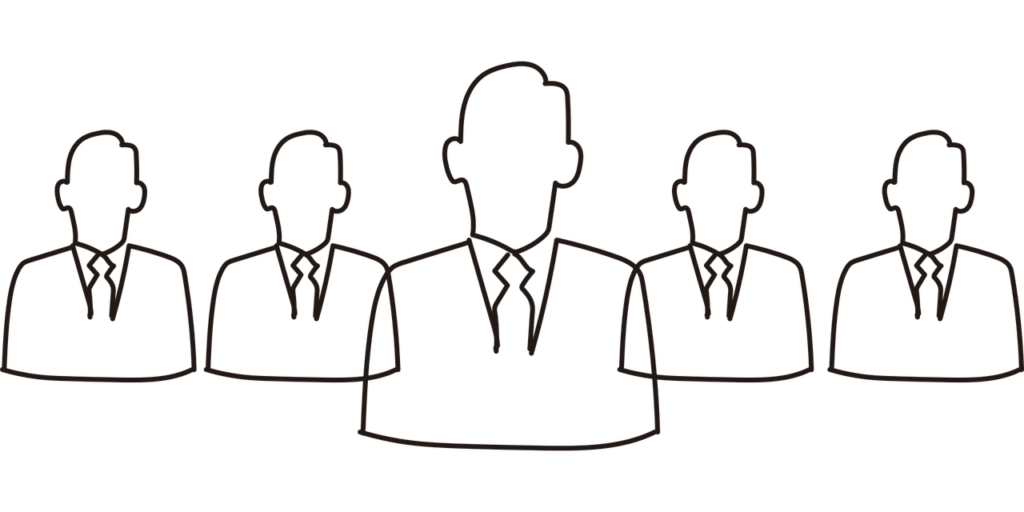
生成AIの導入によって、人事業務は目覚ましく効率化・標準化が進み、本社集中による一括管理も現実のものとなりました。
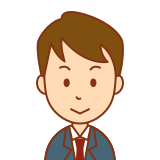
結局 人事はAIに仕事を奪われるのか。それとも何か新しい役割があるのかな

AIを使える人事ほど これから必要とされます。人事の価値はむしろ高まっていきます
ですが、AIが人事のすべてを代替するわけではありません。
むしろ今後は、「AIをどう使いこなすか」が人事部門の力の見せどころになります。
特に注目すべきは、人事部員自身がAIの仕組みや可能性を理解し、自らの手でAIを業務に活かしていけるかどうか。
これはもはやIT部門の仕事ではなく、人事担当者にとっての“必須スキル”です。
AIを使う人事と、AIに使われる人事。その分かれ道に立っている今、私たちは「人に寄り添えるテクノロジー活用」を武器に、人事の可能性を広げていくべきタイミングに来ているのです。
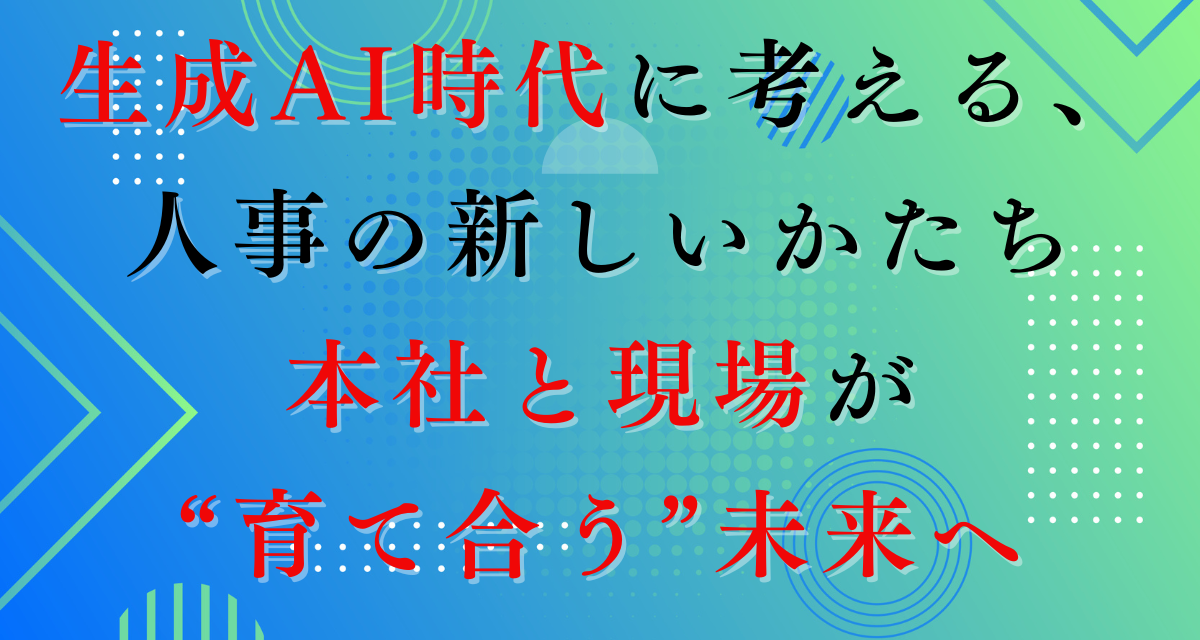

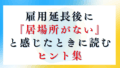
コメント