「あれ? ここはもう自分の居場所じゃないのかもしれない」――。
50代という節目の年齢。これまで会社のために真摯に働き、経験も実績も積んできたはずなのに、ある日突然、自分の存在意義が揺らぎ始める。
異動、評価、世代間のギャップ、そして定年後の不安……それらが静かに、しかし確実に「自分の居場所」が見えにくくなっていく。
この記事では、50代でキャリアの転機を迎えた筆者自身の体験を通じて、「なぜ自分の居場所がなくなったと感じるのか」を深掘りし、その状況を乗り越えるための「心の持ち方」や「行動のヒント」を具体的に紹介しています。
例えば、技術職から人事部への異動による戸惑いや、若手との価値観の違いに感じた孤独、理不尽な評価制度への悔しさ――それらを赤裸々に綴りつつも、マインドセットを切り替え、自ら新たな道を切り拓いたリアルな記録です。
もし今、あなたが「ここにいても意味がないのでは」と感じているなら――。この記事が、再び歩き出すきっかけになれば幸いです。

こんなに頑張ってきたのに…気づいたら、居場所がなくなったような気がする

それはあなただけじゃありません。 一緒にその「違和感」の正体を見つめ直してみませんか
50代、キャリアの曲がり角で感じる「自分の居場所」の揺らぎ
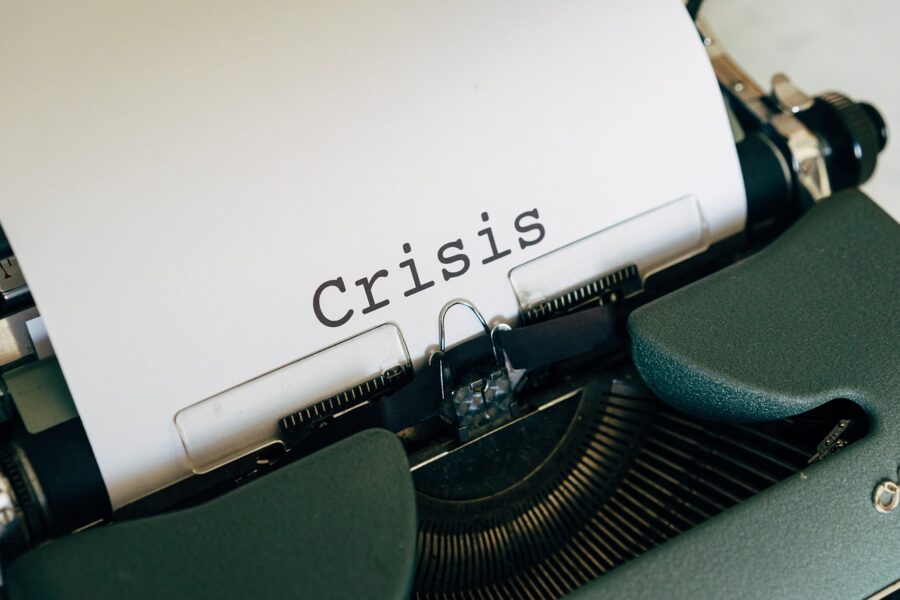
50代は、これまで積み上げてきたキャリアが評価されると同時に、新たな役割や環境に適応しなければならない転換期でもあります。
しかし、変化が大きければ大きいほど、「ここは自分の居場所ではないのでは」と感じてしまうことがあります。
ここでは、そんな“居場所の揺らぎ”が起こる5つの具体的な場面を通して、なぜそう感じるのか、どう向き合うべきかをお話していきます。
突然の異動と新しい役割で感じた「居場所の喪失感」
私は50歳のとき、それまで長く務めていたエンジニア職から人事スタッフへの異動を経験しました。
役職定年ではなかったものの、まったく畑違いの分野に移ることになり、大きな戸惑いを感じました。
それまで積み上げてきた技術や経験が、異動先では直接的に役に立たず、「今の自分は人事という組織の中でどんな価値があるのだろう」と悩むこともありました。
しかも、新しい部署では「エキスパート」として一人で成果を出すことを求められます。
そうした環境の中で、「自分の居場所がない」と感じることがありました。
このような変化は、誰にとっても不安を伴うものです。今まで築いてきたキャリアや人間関係が急にリセットされたような感覚に陥ると、精神的なダメージも大きくなります。

この年齢で慣れない仕事に就くなんて 正直どう向き合えばいいのかわからないですが

その戸惑いは自然なことです。でも視点を変えれば自分の可能性を広げる第一歩になるんです
だからこそ、こうした経験をただの「試練」として受け止めるのではなく、自分自身と向き合い、新たな可能性を見出すきっかけにすることが大切ではないでしょうか。
世代間ギャップにより感じる孤立感
50代になって特に戸惑いを感じたのは、若手社員との「働き方」や「価値観」の違いでした。
たとえば、私たちの世代では、仕事を任されたら納期までに仕上げるのが当然で、必要があれば残業してでも責任を果たすという考えが一般的でした。
しかし、今の若手は「残業はしないのが前提」という意識が強く、納期や品質へのこだわりに温度差を感じることもありました。
「もっと丁寧に仕上げてほしい」と思う場面も少なくありません。
また、コミュニケーションの取り方にも違和感を覚えました。
すぐそばにいるのだから直接声をかければ済むと思うのに、彼らはメールやチャットで連絡してくることが多く、「なぜ話しかけないのか?」と不思議に思ったこともあります。
こうした違いに直面すると、「自分のやり方はもう古いのか」「ここに自分の居場所はあるのか」と感じてしまうことがあります。
しかし、時代とともに価値観も変わるのは当然のことですよね。
相手を否定せず、違いを理解しようとする姿勢が、職場では求められているのだと、徐々に実感できるようになりました。
会社方針の転換で揺らぐキャリアの軸
これは、私の前職で一緒に働いていた人事部の後輩の話です。
彼は、人事のプロを目指して、採用から労務、人材育成まで幅広く経験し、ゼネラリストとして人事全般に精通した管理職へと成長しました。
丁寧にキャリアを積み重ねてきた、まさに「人事のエキスパート」になりました。
ところが、会社が「ジョブ型雇用」へと舵を切ったことで、状況が変わりました。
「これからは専門性が求められる」と急に言われても、「ゼネラリストとして育成されてきた自分は、何を専門にすればいいのか」と、彼は戸惑いを隠せなかったそうです。
さらに不安を感じていたのは、部下の育成です。
人事のすべての仕事を理解したうえでマネジメントすることが大切だと考えていた彼にとって、例えば、採用しか経験のない人が管理職になるのは、「本当にそれでいいのか?」と疑問に思ったそうです。
こうした会社の方針転換は、長年の努力や信念を否定されるように感じてしまうものです。
でも、そんな時こそ、自分の価値を見失わず、変化をどう受け止めていくかが大切なのかもしれませんね。
評価されない現実に、どこか虚しさを感じて
私自身、50歳で長年勤めたエンジニア職から、人事スタッフへの異動を経験しました。
技術の現場を離れ、新たな分野に挑戦することに不安もありましたが、「会社のためにできることがあるなら」と思い、私を受け入れてくれた人事に感謝しました。
ところが人事に異動してみると、そこには厳しい現実が待っていました。
昇進の話は当然なく、上司は年下。そしてある日、人事部長からこう言われたんです。
「人事評価では若い管理職を優先したいと思っています。それで、申し訳ないけど、あなたは定年前には人事考課で、最低ランクをつけることになります」
その言葉通り、月給は1万円下がりました(あの当時の昇給は、3千円~6千円でした)。
正直なところ、定年前といってもそれなりの成果を出していたので、努力が報われないという現実に、どこか虚しさを感じました。
これが、50代で感じる“評価の頭打ち”の現実と理解しました。
定年後を見据えたときの不安と現実
私は10年前、当時勤めていた会社の人事部を定年退職しました。
当時、人事部で管理職だった者には、暗黙のうちに「雇用延長はしないもの」という雰囲気がありました。
実際に、会社側からも「雇用延長は考えていませんよね」と念を押されるような言葉をかけられ、自然と定年退職の道を選ばざるを得ませんでした。
その後、正直に言うと、不安でいっぱいでした。
これからどうやって生きていくのか、再び働く場が見つかるのか――。
幸いなことに、エンジニア時代に携わっていた、いまでは珍しいプログラミング言語「FORTRAN」のスキルが役立ちました。
昔の同僚が立ち上げた会社が、そのスキルを必要とするというので、半年ほど浪人生活を送ったのち、新たな職を得ることができました。
しかし今振り返ると、仮に雇用延長ができていたとしても、「会社から望まれていない仕事や働き方」であったならば、それはそれで、居心地はさらに悪かったかもしれない……そんな風にも今は、感じています。
定年後の働き方、会社に居場所があるかどうか――それは50代の今から考えておくべき、大切なテーマになります。
居場所がないと感じたときに持ちたい「心の整え方」

50代でキャリアの流れが変わると、これまで積み上げてきた自信や誇りが、ぐらつく瞬間があります。
「もう自分は必要とされていないのかもしれない」――そんな思いが頭をよぎることもあるでしょう。
けれど、そうしたときこそ大切なのが「どんなマインドで自分を支えるか」です。
心の持ち方一つで、見える景色が変わり、次の一歩が踏み出しやすくなります。
ここでは、居場所を見失いそうな時にこそ持っておきたい、3つのマインドセットをご紹介します。
【マインドセット1】「変化はチャンス」と捉える
私自身、50歳のときに長年続けてきたエンジニア職から人事部門へ異動になりました。
正直に言うと、最初は戸惑いもありました。
まったく畑違いの世界で、これまでの知識やスキルが活かせるのか不安だったのです。
でも、ある時ふと思ったんです。「これは、自分のキャリアを“自分の意思で切り開く”チャンスなのではないか」と。
それまで私はITの知識や技術にはそれなりに自信がありましたが、それ以外の領域についてはあまり経験できていませんでした。
だからこそ、人事への異動は、組織の仕組みや人を支援するための知識・ノウハウを学べる貴重な機会だと考えるようになったのです。
変化はたしかに怖いものです。でも見方を変えれば、「自分の幅を広げるためのステージ」にもなります。
今思えば、あの異動があったからこそ、私はITと人事の両面から組織を見られるようになりました。
今、環境の変化に戸惑っている方がいたら、ぜひこう考えてみてください――「これは自分のキャリアに新しい可能性を加える、絶好のタイミングかもしれない」と。
【マインドセット2】「過去の経験は消えない」という自信を持つ
私がエンジニアから人事に異動したとき、「この新しい環境で自分は何ができるのだろう」と不安に思ったことを、今でもはっきり覚えています。
でも、最初に任された仕事が、その不安を大きく変えてくれました。
それは、社員や派遣スタッフの残業管理を適正に行うためのシステム開発でした。
私は企画を立て、設計し、情報システム部門に具体的な開発指示を出し、実際の運用まで一貫して手掛けました。
これまでのIT経験があったからこそ、人事の課題を「システムで解決する」アプローチが取れたのです。
そしてこのプロジェクトが、全社的な残業管理の適正化にもつながり、人事の中で私自身の役割を築く第一歩となりました。
新しい職場で、すぐに評価されないこともあります。でも、自分が過去に積み上げてきたスキルや知識は、決して無駄にはなりません。
「いつかきっと、どこかで必ず役立つ」――そう信じて、私は前に進むことができました。

今の職場では何の評価もされないし、自分の過去の経験が無意味に思えるです

あなたが無意味と思う過去の経験は必ずどこかで生きます。表に見えなくても、あなたの中で力になっているんです
今まさに環境が変わり、不安を抱えている方も、どうか自分の歩んできた道に自信を持ってください。
その経験は、あなたの“武器”になる日が、きっと来ます。
【マインドセット3】「他者と比べない」自分軸を持つ
人事に異動した当初、私にとってはまったく新しい世界でした。
正直に言えば、「自分はこの部署で何ができるのか」と、焦りや不安を感じることもありました。
周囲には経験豊富な人事のプロもいれば、若手のスピード感に圧倒される場面もありました。
でも、そんなときこそ私は「他人と比べない」ことを心がけました。
他人と比べてしまうと、どうしても自分の足りない部分ばかりが目についてしまい、自信を失いやすくなります。
人にはそれぞれ異なる強みや背景があり、同じ基準で測ること自体が難しいのだと気づいたのです。
だからこそ、自分には、現場での長年の経験があると信じることが、ブレずに前を向くための支えになりました。
人事の知識はこれから学べばいい。
だけど、現場の実態を肌で知っていることは、すぐにでも活かせる――そう思い、私は現場の視点から積極的に人事に働きかけました。
たとえば、IT業界にありがちな「泥沼プロジェクト」(納期遅れや赤字を招くような案件)について、どうやって早期に察知できるかというノウハウを共有しました。
長時間残業が続くメンバーの動き、プロジェクトの進捗状況、内容の偏りなどから問題の兆しを読み取る方法を、人事部内で提案し、施策づくりに反映してもらったのです。
「人事の経験がないから…」と尻込みしていたら、この貢献はできなかったと思います。
だからこそ、自分ができること、自分にしかない視点――そうした「自分軸」を大切にすることが、変化の中でも自分らしく働くための支えになるのだと、今では強く実感しています。
「自分の居場所がない」と感じたとき、前に進むための行動とは?

心の持ち方が整ってきたら、次は一歩でも前に進むための具体的な行動が大切です。
50代だからこそ、自分から動かなければ、環境は待ってはくれません。でも、ほんの少しのアクションで、状況は確実に変わっていきます。
ここでは、「自分の居場所がない」と感じたときに、実際に試してほしい5つの行動をご紹介します。
【行動1】自分の強みを“見つけて”言葉にする
「私が人事に異動したばかりの頃、新しい職場に馴染めるのか、自分はここで何ができるのか――そんな漠然とした不安を抱えていました。
そんなとき、ふと立ち寄った書店で目に飛び込んできたのが、「さあ、じぶんの才能に目覚めよう」というメッセージでした。
惹きつけられるように手に取ったのが『ストレングス・ファインダー2.0』という本。
すぐに購入し、さっそくアセスメントを受けてみました。
結果、私には「影響力」の資質――つまり、主導権を握り、自分の意見を明確に伝えることで人を動かす力がある――ということがわかりました。
この診断結果は、まさに私の背中を押してくれるものでした。
それまで、自分の強みを客観的に見つめ直す機会がなかったのですが、この体験を通じて、「自分にはこういう力がある」と実感できたことで、新しい職場でも堂々と行動できるようになったのです。
「今の自分に何ができるか」「どんな価値を職場に提供できるか」――そんな自分自身の“棚卸し”は、新たな一歩を踏み出すうえで、何よりの基盤になります。
不安なときこそ、自分の中にある“強みの種”を見つめ直してみてください。
それが、次の行動のエネルギーになります。
ストレングス・ファインダー2.0はこちらから購入できます。
【行動2】信頼できる人と「気持ちを分かち合う場」をつくる
私はずっと、職場では「仲間をつくること」がとても大切だと思ってきました。
どんなに優秀な人でも、一人で抱え込んでいては、心がすり減ってしまいます。
特に私が在籍していた人事部では、それを実感する場面が何度もありました。
月に一度、本社で開催される部長会議。全国から管理職が集まり、組織の課題について話し合うのですが、当時の人事部長は非常に厳しい方で、会議中には痛烈なコメントが飛び交いました。
私の同僚たちは会議後に心を痛め、ぐったりとした表情で席を立つ姿もよく見かけました。
そこで私は、「クールダウンミーティング」という名の飲み会を発案し、会議の後に気軽に集まる場を作ったんです。
このミーティングは人事部長を除いた参加を希望する管理職の集まり、ただ飲むだけでなく、会議のモヤモヤを吐き出す時間――まさに“気持ちのリセット”のための時間でした。
このミーティングは、なんと私の退職まで10年間続きました。退職後も、「あのクールダウンミーティングにどれだけ救われたか」と言ってもらえることが何度もありました。
信頼できる人に話すだけでも、心がふっと軽くなることがあります。
そして、そんな場を自ら作ることもできるのです。
「話せる仲間がいること」――それは、どんなスキルや実績よりも、仕事を続ける上で大きな支えになると思います。
【行動3】新しいスキルを学び、未来を切り開く
人事部に異動してから、私はそれまで以上に「人と接する機会」が増えました。
現場とは違い、人との関係性が中心となるこの仕事に、最初は戸惑いもありました。
というのも、私はどちらかというと、人づきあいや対人コミュニケーションに苦手意識があったからです。
でも、だからこそ思ったのです。「苦手なままではなく、きちんと学び直そう」と。
そこで目指したのが、国家資格キャリアコンサルタントでした。正直、一度目の試験では不合格。
悔しい気持ちもありましたが、諦めずに勉強を続け、二度目の挑戦で合格することができました。
この資格取得は、当時はただ「苦手を克服したい」という思いから始めたものでしたが、後になって振り返ると、私の人生を支え、変えることになった大きな「行動」だったと実感しています。
実際に退職後、このキャリアコンサルタント資格を活かして、対人支援の仕事に就くことができました。
50代だから遅いなんてことはありません。むしろ、経験を積んできた今だからこそ、学びが血となり肉となるます。
もし「今のままでいいのだろうか」と感じている方がいれば、小さな一歩でいいので、新しい学びに踏み出してみてください。
それが、これからの働き方にきっとつながります。
【行動4】小さな成果を積み上げ、自分の「存在意義」をつくる
人事に異動して間もない頃、私は「この職場で自分は何ができるのか」「どうすれば人事の中で成果を出し、仲間たちから信頼を得られるのか」と、日々自問していました。
新しい環境で、いきなり大きな成果を上げるのは難しい。
だからこそ私は、まずはできることから取り組み、小さな成果を一つひとつ積み上げていくことを意識するようになりました。
もともと私は、システム開発の経験がありました。
そのスキルを活かして最初に取り組んだのは、残業管理システムの構築です。
そしてそれだけではなく、マイクロソフト社のAccessを独学で学び、社員の工数管理や、長時間残業者のデータを抽出・分析できるシステムも自作しました。
それらのデータを人事部だけでなく、事業ラインとも共有できる仕組みにすることで、「現場と人事をつなぐ橋渡し役」として、少しずつ信頼されるようになりました。
最初は目立たない仕事でも、コツコツと積み重ねた小さな成果が、やがて「自分の居場所」につながっていくのです。
今、居場所が見つからないと感じている方も、まずは目の前の小さな課題に一つずつ向き合ってみてください。
その積み重ねが、きっと道を開いてくれます。
【行動5】会社の外に踏み出し、学びとつながりで未来を切り開く
国家資格であるキャリアコンサルタントの資格は無事に取得できたものの、実際に対人支援のスキルをさらに高めたり、それをビジネスとして広げていくには、会社の中だけでは限界がある――そう強く感じるようになりました。
そんなとき、資格取得の際にご指導いただいた多田健次先生が立ち上げた「対人支援のプロを育てる複合型研究施設 Shien.lab(シエン・ラボ)」というコミュニティの存在を知り、私はそこに参加することを決めました。
ここでは、単なるスキル研修にとどまらず、自分の強みの言語化(ブランディング)や、ブログ・ホームページの作成方法、オンライン講座の開催方法など、これまでの会社人生では触れてこなかった分野の学びが得られました。
何より大きかったのは、同じ志を持つ仲間たちとの出会いです。会社では味わえない、オープンで温かいつながりの中で、自分の可能性を広げることができました。
この経験が、私の退職後の働き方――キャリアコンサルタントとしての独立や対人支援の仕事――へと直結しています。
もし今、「このままでいいのだろうか」と感じているなら、一歩、会社の外に目を向けてみてください。

会社の中でしか学んだことがなくて 外で学ぶなんて自分にできるのか不安です

少し勇気は要りますが 会社では得られない学びや視点が見つかることもあります。新しい出会いや学びが、きっとあなたの次のステージを照らしてくれます
まとめ:50代は「再スタート」のチャンス

50代で感じる“会社に居場所がない”という感覚は、決して一時的な錯覚ではありません。
それは、積み上げたキャリアが揺らぎ、役割の変化や制度の壁によって、自分の価値が見えづらくなる時期だからです。
異動による孤独、評価の頭打ち、会社の方針転換による戸惑い、定年後の不安――これらは多くの人が直面する現実です。
しかしその一方で、心のあり方を整え、小さな行動を積み重ねることで、自分らしい「居場所」を再構築することも可能です。
過去の経験は消えず、他人と比べず、自分軸を持つこと。
そして、信頼できる人と気持ちを分かち合い、学びを通してスキルを磨くこと。それらの積み重ねが、50代以降の人生をより豊かなものへと変えてくれるのです。
「もう遅い」ではなく、「ここからが本番」。
50代は、自分らしい生き方に再び舵を切る“再スタート”の絶好のタイミングなのです。

この年齢から何かを始めても、もう遅いんじゃないかって思ってしまいます

遅いなんてことはありません 今までの経験があるからこそ、これからの一歩が踏み出せるのです
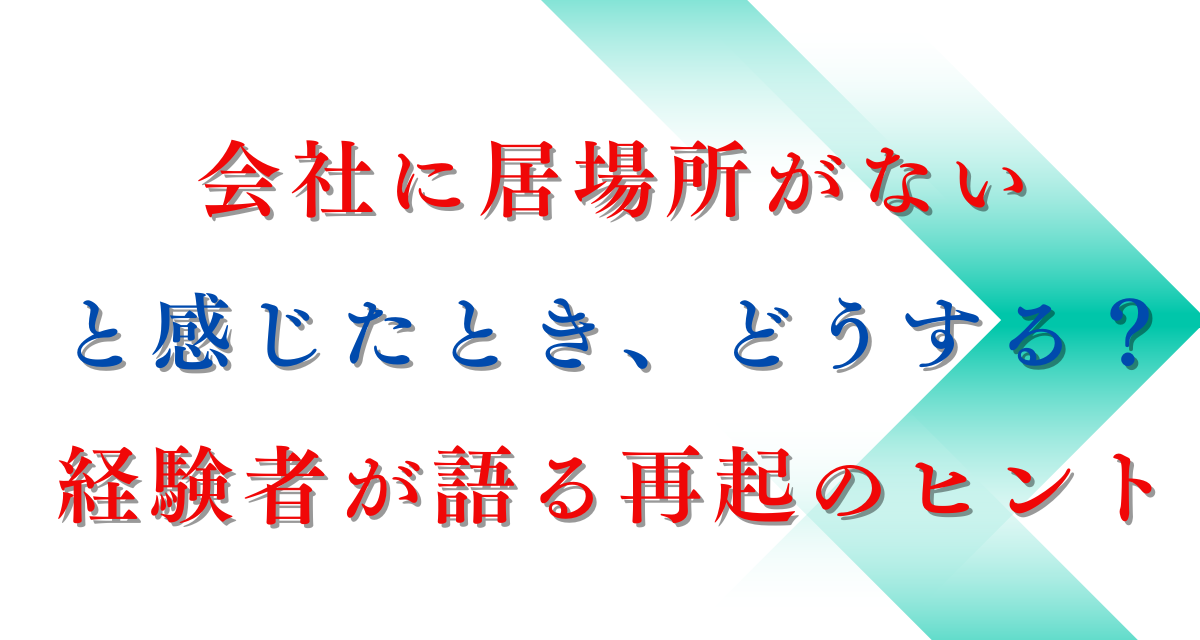
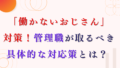
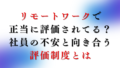
コメント