中高年になると、健康や仕事、家庭などのさまざまな場面で「これまで通りではいかない」と感じる瞬間が増えてきます。
人生の折り返し地点を過ぎ、自身の価値や存在意義について改めて考え直すこともあるでしょう。
本記事では、そうした中高年が直面する危機の背景を踏まえながら、実際に私自身を含めた4名の中高年が経験したリアルなエピソードをご紹介します。

同じように悩んでいる人が本当にいるのか不安でたまらないんです

はい 実際に似た境遇に直面した方々の体験から共に考えることができる内容になっています
それぞれがどのように苦境に向き合い、どんなきっかけで乗り越えてきたのか。
中高年世代にとって、危機は“終わり”ではなく“転機”にもなり得るという視点から、今後の人生を見つめ直すヒントをお届けします。
中高年の危機とは

人生100年時代と言われるようになった今でも、中高年期は大きな節目として、誰にとっても少なからず「危機」の要素を孕んだ時期です。
体力の衰えや家族構成の変化、職場での役割の終わり──それらは、日々の生活の中で徐々に、しかし確実に私たちに変化を突きつけてきます。
私自身、定年を前にしてからさまざまな出来事を経験し、自分自身のあり方を深く見つめ直す機会が増えました。
それは決して楽な過程ではありませんでしたが、その中には新たな気づきや、生き方の再構築につながるヒントもありました。
中高年の危機とは、決して「終わり」ではありません。
それはむしろ、自分自身を再定義し、次の人生をより豊かに生きるための「問いかけ」の時期です。
そしてその問いかけは、次の3つの変化として現れてきます。
【変化1】健康不安の増加と生活習慣の見直し
中高年期になると、体力の衰えや疲れの取れにくさ、生活習慣病のリスクの増加など、身体的な変化が顕著になります。

最近疲れが取れなくて 年齢のせいだと諦めかけています

その気づきこそが変化の第一歩です。 今の生活を見直すチャンスとして向き合ってみましょう
私自身も、60歳の定年を迎えた直後、それまでの緊張感に満ちた会社生活から解放されたせいか、心身のバランスが崩れたのか、一気に体調を崩しました。
ひとつは、長年だましだまし杖をついて通勤や出張をしていた変形性股関節症が悪化し、ついに人工関節への置き換え手術を受けることになりました。
もうひとつは、自己免疫が原因で肝臓の胆汁をつくる機能を壊してしまう指定難病「胆汁性胆管炎」と診断され、確定までに約2か月を要しました。
現在は治療薬であるウルソを1日9錠服用しながら病気と向き合っています。
こうした体験を通じて、健康であることのありがたさを痛感すると同時に、自分の生活習慣を見直す大きなきっかけにもなりました。
定期的な運動やバランスの取れた食事、定期検診を怠らないことなど、小さな積み重ねが将来の健康を支える大きな土台になると、身をもって実感しています。
現在は、週に1度トレーナーをつけたジムに通い、器具の重さ管理をしてもらいながら、体力強化にも努めています。
【変化2】家庭や職場での役割の変化と喪失体験
この時期は、子どもが自立し、親としての役割が一段落する一方で、親の介護や看取りという新たな役割が始まることがあります。
私自身、まさにその転換期を経験しました。
父は私が48歳のときに肺がんを患い、愛媛県の内子という町(松山から車で1時間ほど)で闘病していました。
当時はまだしまなみ海道も整備されておらず、広島から病院まで片道6時間かけて、毎週土日には見舞い行ってました。
そして、父はその後、静かに息を引き取りました。
それから5年後、今度は母が脳腫瘍で倒れました。
私が53歳のときでした。救急搬送されてから約半年間、病院と内子の実家の片づけを並行して行う必要があり、再び毎週末は内子との往復でした。
やがて母もこの世を去り、5年間のうちに両親を続けて見送ることになりました。
肉親の死は、心身ともに深く響きます。
葬儀が終わって日常に戻っても、胸の内にはぽっかりと穴が空いたような寂しさと空虚感が残りました。
そして、死というものをこれほどまでに身近に感じたのは初めてでした。
家庭でも職場でも、かつて担っていた役割が終わっていく中で、「自分にはもう何が残っているのか」と立ち止まることもありました。

誰かの役に立てていた実感がなくなって 自分の存在が薄れていくようで怖いです

役割が変わっても あなたの存在の価値は変わりません 。新たな形でつながりを見つけていきましょう
しかし同時に、それを機に人生を見つめ直し、新しい価値観や人との関わりを築くきっかけにもなったと感じています。
【変化3】自己評価の揺らぎと新たな生きがいの模索
50歳を過ぎた頃から、会社人生における大きな転換期が訪れます。
私自身の経験でも、50代後半になると役職定年を迎え、これまで担ってきたポストを後輩たちに引き継ぐことになりました。
かつては自分の判断や責任で物事を動かしていた立場から一歩引き、若手にチャンスを与える側に回ることになります。
その一方で、企業では「ジョブ型雇用」が進み、ポジションに依存せず個人の専門性や成果がより強く求められるようになりました。

肩書きがなくなってから 自分の価値がよく分からなくなってしまいました

肩書きではなく あなた自身が持つ力に目を向けてみましょう。 本当の価値はそこにあります
そうした変化の中で、「これまでの経験や肩書きでは通用しないのではないか」「自分の存在価値はどこにあるのか」といった不安が心に芽生えます。
周囲の仕事の流れから取り残されたような感覚や、職場での「居場所のなさ」を感じることもあります。
こうした自己評価の揺らぎは、中年期ならではのものです。
若さを失っていく現実と向き合いながら、これまでの人生や働き方を振り返る時間が増えてきます。
しかしこの時期は、単なる後退ではなく、人生の意味を見つめ直し、新たな目標や生きがいを探る貴重な機会でもあります。
私自身も、以前のような立場にいなくても、自分の強みを活かして後進を支えることに生きがいを感じるようになりました。
また、新しい分野への学び直しや、地域社会との関わりなど、第二の人生に向けた挑戦も始めています。
中年期は「揺らぎ」の時期であると同時に、「再定義」と「再出発」のタイミングでもあります。
変化を恐れず、自分の可能性を信じて一歩を踏み出すことが、新たな生きがいにつながるのです。
中高年の危機の具体的事例から学ぶ、人生の転機

人生100年時代と言われる現代においても、中高年期は決して平坦な道のりではありません。
仕事、家庭、健康、人間関係――これまで積み重ねてきたものが大きく揺らぎ、「このままでいいのだろうか」と立ち止まる瞬間が誰にでも訪れます。
ここでは、私自身を含めた中高年世代が直面したさまざまな「危機」の具体的な事例を4つご紹介します。
いずれも、行き詰まりや喪失感を感じながらも、自らの内面と向き合い、乗り越えることで新たな生き方へと舵を切った実話ばかりです。
リアルな体験を通じて見えてくるのは、「危機」は必ずしも終わりではなく、新しい人生の幕開けとなる“転機”にもなり得るということ。
そのヒントを、次の4つのエピソードから読み解いていきましょう。
【事例1】努力が報われないという停滞感
──上昇停止症候群からの私自身の転機──
私は長年、同じ職場で真面目に努力を重ねてきました。
部門のリーダーとして、数字や成果を出すことに全力を尽くし、チームを引っ張り、上層部の期待に応えることを何よりも優先してきた日々でした。
しかし、バブル崩壊など外的要因により、長年関わっていたプロジェクトが突如解散となり、その後、異動を命じられました。
その瞬間、「これまで築いてきたキャリアが一気に崩れた」と感じました。
努力が無意味だったように思え、自分の存在価値さえ揺らぐ――まさに「上昇停止症候群」と呼ばれる状態に、自分が陥っていることを実感したのです。
そこから私がまず取り組んだのは、自分のキャリアを一度立ち止まって振り返り、「会社でどれだけ成果を出したか」ではなく、「これから自分は何を大切にして働いていきたいのか」という視点への転換でした。
リーダーとして走り続けてきた私は、これまで“評価”や“成果”に強く依存していたことに気づきました。
しかしその一方で、自分の中に確かにあった「人に影響を与える力」、つまり主導権を握り、自分の考えを明確に発信し、周囲を巻き込んで動かす影響力こそが、自分の本来の強みであったことを再認識したのです。
そこで私は、「上から与えられる役職」や「数値目標」だけにとらわれるのではなく、たとえ役職が変わっても、自分の意志で発信し、行動し、周囲に良い影響を与えていくことを新たな目標にしました。
小さな場でも、自分の思いを伝え、共感を得て、チームの空気が前向きに変わっていく――そうした経験が、再び私の働く意味や喜びとなっていきました。
この変化をきっかけに、私は一つの肩書に縛られず、自分の「影響力」という強みを軸に、新しい働き方へと舵を切ることができました。
かつてのように数字だけを追うのではなく、「人に影響を与える喜び」を実感できる仕事に向き合う姿勢へと、自然に変わっていったのです。
【事例2】左遷による燃え尽き症候群
──拾ってくれた場所で見つけた、第二のキャリア──
私は50歳のとき、部長として事業部のために全力を尽くしていました。
現場に足を運び、部下の声に耳を傾け、数字と成果の両立を追い求める日々でした。
自分なりに誇りを持って働いていましたが、ある時期、事業部長との関係が悪化し、その結果として左遷同然の異動を命じられました。
そのときは本当にショックでした。
自分が積み重ねてきたものが一気に崩れ落ちたように感じ、深いむなしさに包まれました。
「これ以上頑張っても、意味があるのだろうか」と、まさに燃え尽き症候群の状態に陥り、心にぽっかりと穴が開いたような感覚を覚えました。
そんな私を拾ってくれたのが、思いもよらなかった人事部でした。
それまでとはまったく異なるフィールドでしたが、私はこの異動を「会社内転職」と前向きに捉えることにしました。
人事の仕事は初めてでしたが、私はそれまでのSE時代の経験やシステム開発のスキル、そして何より現場を理解しているという強みを活かせる場面が多くあることに気づきました。
勤怠管理システムの改善、配置・評価における現場の視点の導入、社内研修プログラムの設計など、システムと人の両面に関わってきた私だからこそできる仕事が、ここにはありました。
「異動先で腐るのではなく、自分の経験を“翻訳”して、新しい環境に活かす」――この考え方が、私を救ってくれました。
それからの10年間、私は人事部で定年を迎えるまで働きましたが、自分なりに“結果”と“意義”の両方を残せたと感じています。
かつてのような目立つポジションではありませんでしたが、裏方として組織を支え、社員一人ひとりの成長やキャリア形成に関われたことは、私にとって大きな喜びとなりました。
左遷という現実は、確かに私の心を折りかけました。
しかし、それがなければ出会えなかった人、できなかった経験があり、今となっては「第二のキャリアの始まり」だったと心から思えます。
【事例3】技術革新への対応の困難さ
──スキルギャップを越えて見つけた“つなぎ役”という新たな価値──
私の前職の後輩に、50歳を迎えたベテランのエンジニアがいました。
彼は長年、組み込み系のソフトウェア開発一筋で、現場での信頼も厚い技術者でした。
しかし、会社がAI技術を本格的に導入する方針を打ち出したとき、状況は大きく変わりました。
業務の主軸が、従来のC言語やファームウェア開発から、Pythonや機械学習モデルの活用へと移行する中で、彼は強い戸惑いを感じていました。
特に若手社員たちは、学生時代からAIやデータサイエンスに親しんできた世代で、TensorFlowやPyTorchを自在に扱い、新しいツールの習得も早い。彼は「彼らとは話す言語が違う」と感じるほど、スキルギャップに圧倒されたと話していました。
その結果、会議でも発言が減り、若手が中心の開発チームから徐々に距離を置くようになっていきました。
上司からの評価も下がり、自分の居場所を見失いかけていた彼ですが、ある日ふと、「このままでは終われない」と一念発起します。
彼がまず取り組んだのは、「基本に戻る」ことでした。AI技術に対する苦手意識を克服するために、仕事終わりにオンライン講座でPythonを基礎から学び直し、社内で開かれていたAI勉強会にも毎回参加するようになりました。
また、自分が得意としてきた制御系の知識とAIの応用領域との“橋渡し”に目を向けるようになり、現場の課題にAIをどう活かせるかという視点で企画提案を始めました。
やがて、若手のAIエンジニアとペアを組んで進めた「予知保全システム」のプロジェクトが社内で高く評価され、再び彼の存在感が増していきました。
若手の技術を引き出し、自身の経験を活かす“つなぎ役”としての新しいポジションを見出したのです。
この後輩の姿から私が学んだのは、「変化に遅れたからといって、終わりではない」ということです。
スキルのギャップを受け入れ、学び直す姿勢を持つことで、自分らしい新しい価値を築くことができる。
その第一歩は、プライドを捨てて、素直に学ぶことなのかもしれません。
【事例4】子どもの独立による空虚感
──「空の巣」から見つけた、自分自身を取り戻す時間──
私の前職の後輩に、家庭と仕事を両立して頑張っていた女性社員がいます。
彼女には一人娘がいて、大学進学を機に地元を離れ、名古屋で暮らし始めました。
大学時代は、帰省や母娘の行き来もあって、まだ「つながり」が感じられる距離感でした。
しかし、娘さんが名古屋の企業にそのまま就職し、社会人として自立した後、状況は一変します。
連絡の頻度も減り、帰省もほとんどなくなったことで、彼女の心にはぽっかりと穴が空いたような感覚が広がりました。
これはまさに、「空の巣症候群」と呼ばれる状態です。
空の巣症候群とは、子どもが独立して家を出た後、それまで“母親”としての役割に深く根差していた自分の存在が、急に不確かに感じられ、孤独感や喪失感に襲われる状態を指します。
彼女もまた、毎日の生活にハリがなくなり、ふとした瞬間に「私はこれから何を支えに生きていけばいいのだろう」と、自分の居場所や存在意義を問い直すようになったといいます。
そんなとき、転機となったのが、地域のジムでのレッスンプログラムへの参加です。
最初は口コミで評判の「ヨガ・ピラティス」や「ズンバエクササイズ」のクラスに出てみました。
音楽に合わせて身体を動かすズンバでは、ステップや振り付けを覚える楽しさがあり、ヨガ・ピラティスでは呼吸を整えることで心と体の両方に穏やかなリラックスを感じられたそうです。
それが習慣になり、次第に「ボディパンプ(ウェイトを使った筋力トレーニング)」「HIIT(高強度インターバルトレーニング)」「アクアエアロビクス」など、多様なレッスンプログラムにも挑戦するようになりました。
今では休館日以外はほぼ毎日、異なるプログラムをこなしており、クラスが終わるころには達成感と爽快感で満たされる日々を送っていると言います。
このような身体を動かすレッスンを通して、彼女は空虚感が少しずつ薄れていくのを実感しました。
クラスメイトと顔を合わせる時間ができて、自然と会話が生まれ、「ああ、私にもこういう居場所があった」と思えるようになったそうです。
彼女は今、「娘が巣立ってくれたからこそ、自分自身の時間を大切にすることを学べた」と、笑顔で話してくれました。
空の巣症候群は、多くの親が経験する自然な心の反応ですが、それを通じて「自分の人生を見つめ直す転機」にできるかどうかが、心の在り方を大きく変えるのです。
後輩のように、新しい趣味や人とのつながりを見つけることで、第二の人生に新たな彩りを加えることができるのです。
まとめ
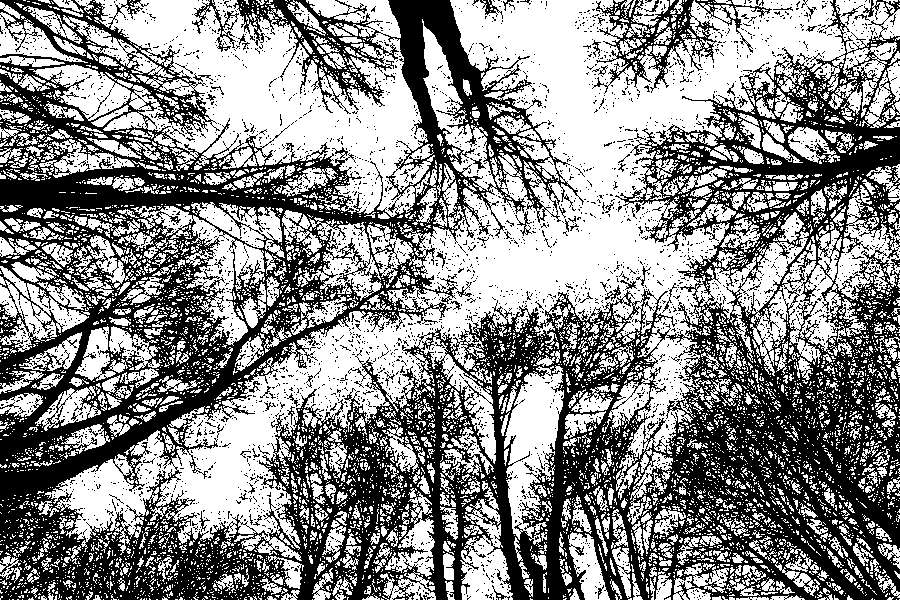
中高年期に訪れる危機は、誰にとっても避けがたい「人生の節目」です。
健康や家庭、キャリアにおける変化の中で、心が揺らぎ、戸惑いを感じることは自然な反応です。
しかし、そうした不安や停滞を「転機」と捉え、これまでの価値観を見直すことで、第二の人生に新しい意味を見出すことができます。
今回ご紹介した4つの事例が示すように、自分と向き合う勇気さえあれば、どんな変化も自分らしく乗り越えていけるのです。

私にもそんなふうに人生を前向きに捉え直せる日が来るでしょうか

もちろんです。 一歩踏み出す心がけさえあれば どんな人にも新たな道は開けます
以下の記事では、中高年の危機を克服するための心構えと具体的な行動について詳しく解説します。
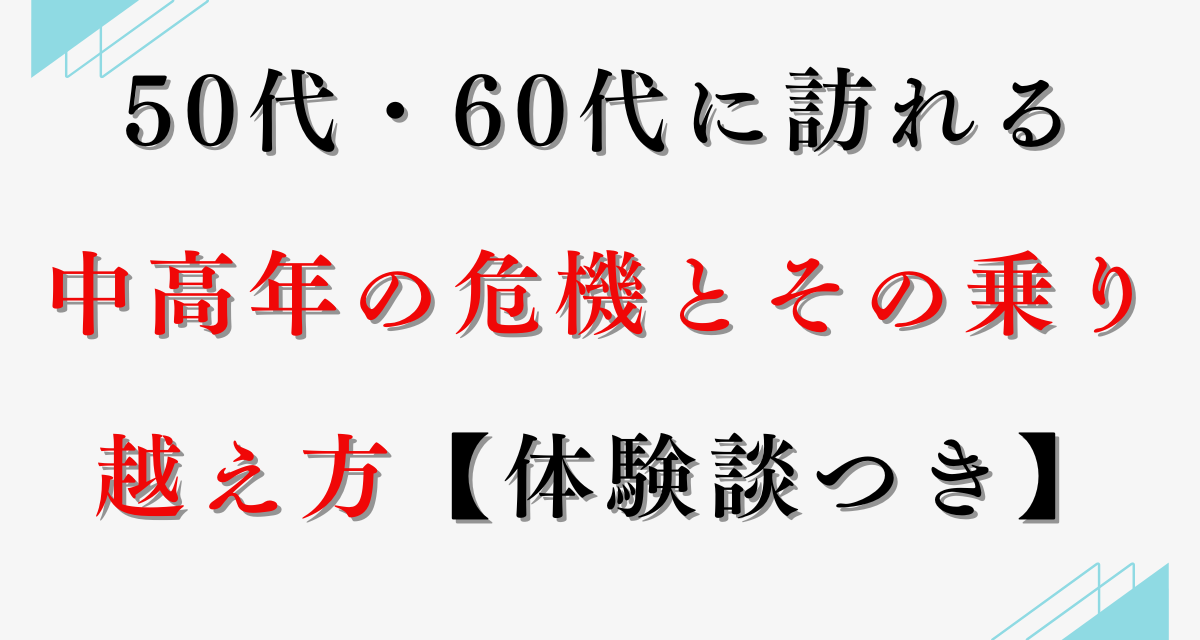
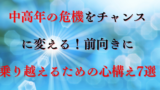
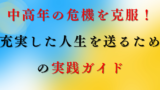
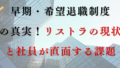
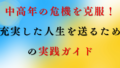
コメント