「自分はまだまだやれると思っていたのに、会社から『外の道を考えてはどうか』と言われるなんて…」

希望退職って、結局は辞めさせられることなんですよね…?

そう感じるのも無理はありません 。でも制度の仕組みを知ることで見えてくる希望もありますよ
早期・希望退職制度――その名前からは「選択の自由」があるように見えるかもしれませんが、実際には非常に重たく、つらい決断を迫られる制度です。
とくに「Cランク」(注)と評価された社員にとっては、「これまでの努力や会社への思いが評価されなかった」という現実を突きつけられ、心に深い傷を残すことになります。
(注)Cランク社員とは、早期・希望退職制度において、会社側が「この機会に退職してほしい」と考える社員のことで、制度運用上の判断により選別されます。
私自身、20年前にIT企業の人事として、この制度の運用を担当しました。
事業部が付けたCランクの社員に、会社からは「応募を促すように」という明確な使命が与えられます。
ただ、面談の場に座っているのは、これまで共に働いてきた仲間でもあります。
この人が辞めるもらうことは、本当にその人のためになるのか?
人事としての責任と、一人の人間としての葛藤。その狭間で、私は悩みました。
この記事では、制度の裏にある企業の戦略、面談の進め方、Cランクとされた方々が直面する葛藤、そして面談する側の苦悩まで、現場で実際に経験したリアルな声をお伝えします。
もし今、あなたが厳しい選択の中にいるとしたら――この内容が、少しでも考える手助けとなれば幸いです。
「早期・希望退職制度」とは何か?――私の経験からお伝えします

「リストラ」と聞くと、多くの方がネガティブなイメージを持たれるのではないでしょうか。
実は、私もその一人でした。
システムエンジニアとして働いていた当時は、自分がリストラに関わるような立場になるとは、夢にも思っていませんでした。
ところが、20年前にIT企業で人事部へ異動になり、その翌年には会社の業績悪化により、早期・希望退職制度の運用に携わることになったのです。
この制度は、企業が経営改善や人件費削減のために実施する、人員整理の一環です。

制度って言っても、やっぱりリストラでしょ…?

確かに制度の性質は厳しいものです 。でも自分にとって有利に使える可能性もあるんですよ
ただし、強制的な解雇ではなく、特別退職金や転職支援サービスといった“インセンティブ”を提示して、社員の自発的な退職を促す形式を取ります。
私の会社では、1年分の年収を退職金に上乗せする制度が導入されました。
さらに、提携している2つの転職支援会社のどちらかを選び、転職サポートを受けられる仕組みも用意されていました。
その支援は「就職が決まるまで継続される」と説明して、早期・希望退職制度を利用しようと考えている社員への安心材料としていました。
早期・希望退職制度の導入と実施のステップ

早期・希望退職制度を円滑に導入・実施するには、明確な方針と段階的なプロセスが欠かせません。
特に社員一人ひとりの人生に関わる繊細な取り組みであるため、十分な準備と丁寧な対応が求められます。
ここでは、制度実施の全体像を5つのステップに分けてご紹介するとともに、Cランクの気持ちや、面談担当者が抱える苦悩と現場のリアルについてもお話していきます。
【ステップ1】全社の目標設定と削減人数の算出
会社が、早期・希望退職制度を導入するとき、最初に行うのは、全社的にどれくらいのコストを削減したいのかを明確にすることから始めます。
そして、そのコスト削減に見合う人数を割り出します。
次に、その削減すべき人数を事業部ごとに割り当てるのです。
これが、早期・希望退職制度で応募してもらう「目標人数」となります。
その後、各事業部(直接部門・間接部門問わず)で、社員一人ひとりの評価や役割に基づいてランク分けを行い、そのランクに応じた面談を進めていきます。
これらの面談では、社員に自身の現在の立場や会社の状況を理解してもらい、今後のキャリアについて前向きに考えるきっかけとしてもらうことに重点をおいています。
そのため、会社としては、現実を正しく伝えた上で、社員が自らの将来を主体的に見つめ直すよう促すことになります。
このプロセスの中で見逃してはならないのが、社員の心の負担です。
退職を勧められる側の社員にとってはもちろんですが、逆に、退職を促す立場に置かれた社員にとっても、そのストレスは決して小さなものではありません。
お互いにとって非常に繊細な場面であり、対応を誤ると職場全体の信頼関係にも影響が出てしまいます。
だからこそ、制度の進め方は単なる手続きではなく、人と人との関係性に十分に配慮した、思いやりのある対応が不可欠になってくるのです。
しかし、早期・希望退職制度に応募してくれとは、退職勧奨と同じ意味なので、面談はついつい厳しいものになってしまうんですよね。ほんとに!
【ステップ2】社員のランク分けによる人材評価
私の会社でも、早期・希望退職制度を進める際に、事業部内で社員を3つのランクに分ける作業が行われていました。
これは、制度の進行において避けて通れない、非常に繊細で難しいプロセスの一つです。
私自身は、このランク分けの選定作業には関わっていません。
社員のランクは、それぞれの事業部で担当役員、事業部長、部長等の話し合いで決めていきます。
ランクは大きく3つに分類されます。
- Aランク:「今後の会社のために、ぜひ残ってもらいたい人」⇒ 組織に欠かせない人材
- Bランク:「残っても辞めても、どちらでも構わない」という立場の人
- Cランク:「この機会に応募して退職してもらいたい」と考えられる社員
Cランクに入る人は、「2年連続で人事考課や賞与の評価が最低だった社員」「組織の中で継続的に問題を起こしている、いわゆる「問題社員」」も対象になります。
また、ランクによってその後の面談の内容や対応が異なるため、社員は「自分が会社からどう見られているのか」を面談の場ですぐに察することになります。
こうしたランク付けにはどうしても主観が入りやすく、面談を通じて自分の立場を認識することで、社員の間に不公平感や将来への不安が生まれることは避けられません。
私自身、以前は事業部門で働いていたことがあり、そのとき一緒に仕事をしていたメンバーのことは、人事部に異動したあとでも大体覚えています。
あるとき、面談に使うリストを見て、「〇〇さんがCランクに評価されている」と知って、驚いたことがあります。
というのも、私の中では「〇〇さんは真面目で、与えられた仕事をきちんとこなす人」という強い印象があったからです。

真面目にやってきたのに…Cランクなんて納得できない…

あなたの頑張りは間違いなく意味があります 。評価と実力は必ずしも一致しないこともあるんです
まさかCランク評価を受けているなんて、想像もしていませんでした。
もちろん、事業部としての判断や評価の基準があるのは理解しています。
ただ、会社人生の中では運・不運といった要素もつきまとうものだと思います。
そうした中で、自分が持っていた印象とのギャップに、正直なところ戸惑いを感じたことを、今でもよく覚えています。
【ステップ3】面談対象者と面談担当者の役割
今回の面談は、早期・希望退職制度の対象となる方全員に対して行われます。
私の会社の場合、対象となるのは、「45歳以上かつ5年以上勤務している社員」の方々でした。
役職やランクに関係なく、該当する方は全員が面談の対象です。
では、誰が面談を行うのでしょうか?
面談は、基本的に「事業部の部長クラス以上の方」と「人事部の管理職」の2名で進められます。
このうち、主に話を進める役割を担うのは事業部の方です。
というのも、面談対象の社員に対して最も近くで日々の業務を見てきたのが事業部であり、今回のランク付けも事業部が中心となって行ったためです。
一方で、人事はサポート役として面談に同席します。
ただし、実際には、面談の進行に慣れている人事が、面談全体を円滑に進めるためのリードを取る場面も多くあります。
つまり、「事業部が責任をもって社員と向き合い、人事がそのサポートをする」というのが基本的な役割分担です。
【ステップ4】面談担当者の事前準備と研修内容
今回、当社で初めてとなる「早期・希望退職制度」の実施にあたり、面談を担当する事業部や人事のメンバーの多くが、リストラの経験はありませんでした。
そのため、「どう伝えれば応募してもらえるのか」という点で、面談する側も非常に悩み、準備が必要でした。
特に苦労したのが、Cランクと位置付けられた社員への対応です。
Cランクとは、会社として将来的な戦力と見なしていない、いわば退職を強く勧めたいと考える対象の社員層です。
しかしながら、ストレートに「辞めてほしい」と言うことはできません。
いかに制度の趣旨を理解してもらい、納得のうえで応募してもらうかが、面談者にとって最大の課題でした。
そのため、会社はまず、事業部の面談担当者および人事の管理職全員を対象に「リストラ専門のコンサルタント会社」の研修を1日かけて受けさせました。
面談の進め方や、発言において注意すべき点(特に言ってはいけない表現や態度など)を徹底的に学びました。
使用された資料は、研修後に全て回収され、機密性の高い内容でした。
さらに、コンサル会社と社内の経験者が作成した「想定問答集(Excel形式)」も配布されました。
10数ページにわたる内容で、Cランク社員への対応についても多くのシナリオが盛り込まれており、面談時に資料の持ち込みができないことから、内容は暗記レベルで準備しました。
このようにして、特にCランクの社員に対しては、「会社としての意思をにじませつつも、表現には十分に注意しながら制度への応募を促す」という難しい役割を、準備を重ねた上で行うのです。
【ステップ5】ランク別の面談対応方針
面談では、ランク付けされた社員ごとに、会社としての対応が異なります。
まず、Aランク・Bランクの社員については、面談で「会社に残ります」と明言された場合、それ以上のやり取りは行いません。
つまり、その場で面談は終了します。
一方で、もしAランク社員が制度への応募を希望した場合には、会社は基本的に慰留の姿勢を取ります。
週に1回ほどの面談を継続し、翻意を促す対応を取るのが通例です。
会社としては、今後も戦力として期待しているからです。
Bランク社員の場合も、同様に制度への応募を希望した際には慰留を試みることがありますが、本人の意思が固いと判断された場合には、それ以上の引き止めは行いません。
そして、最も対応が異なるのがCランク社員です。
Cランクに位置付けられた社員には、面談の中で、「今後、会社での活躍の場が限られてくる可能性がある」といった伝え方をします。
さらに、「社外で新しいキャリアを築くことも一つの選択肢ではないか」と、制度への応募を促す方向で話を進めていきます。
それでも応募の意思が示されない場合には、「今の業務を継続することは難しくなる」といった表現も使いながら、応募してもらえるまで、面談を繰り返し行うことになります。
Cランク社員に対する面談は、事実上の退職勧奨としての性質が強くなります。
Cランク社員の気持ち
Cランクと評価された社員にとって、面談は心に痛みを残すような、精神的に大きな負担となる経験です。
多くの方は、これまで長年会社のために努力を重ねてきたという自負や、会社に対する愛着を持っています。
そうした中で、「これからは会社での活躍の場が少なくなる」といった言葉をかけられることは、自分の存在や貢献が否定されたように感じられ、大きなショックとなります。
また、日々の仕事に真面目に取り組んできたにもかかわらず、勤務態度や会社への貢献が「評価されなかった」と感じることで、理不尽さや納得のいかない思いが心に残ります。
そして、なぜ自分がCランクなのか――その理由が明確に説明されない場合には、上司や会社への疑念や不信感も強まります。
さらに、「外で新しいキャリアを築くべきだ」と促されても、年齢や経験、家族の状況などを考えると、退職後の生活や再就職に対する不安が募る一方です。

今さら再就職なんて無理…家族にもなんて言えば…

不安な気持ちを抱えて当然です。 でも新しい道には意外な可能性も広がっているんですよ
先の見えない将来に対する恐怖や、自己否定感にさいなまれることも少なくありません。
このように、Cランク社員にとっては、自身の価値を揺るがされるような深い精神的ダメージを伴うことが多いのです。
面談担当者の苦悩と現場のリアル
Cランクと評価された社員の皆さんにとって、面談は大きな精神的負担になることは、私たちも理解しています。
しかし実は、面談を担当する側もまた、深い苦悩を抱えているのです。
会社としては、一定の応募者数を確保するという「目標値」が設定されています。
そのため、人事側は週1回の朝会で、Cランク社員の応募状況を逐一報告し、さらに月1回の人事部長会議では、全国の人事担当者が大阪に集められ、「なぜ応募に至らなかったのか」「今後どう説得するか」といった説明を求められるのです。
そのプレッシャーの中で、面談を担当する事業部や人事のメンバーも、日々悩みながら対応しています。
特に、かつての部下だったり、一緒に汗を流して働いてきた社員に「会社を去ってほしい」と伝えることは、想像以上につらいことです。
応募してもらうまで、面談は週1回のペースで繰り返されます。
その中で、焦りやストレスから、つい厳しい言葉をかけてしまうこともあります。
そしてその直後、自分自身の発言に後悔し、自責の念にかられる――その繰り返しです。
実際に、私自身も面談の終盤には、夕方から悪寒がし、38度近い発熱に悩まされる日々が続きました。
病院を受診すると「尿路感染症」と診断され、治療に通うことになりました。
身体にまで影響が出るほど、面談者の精神的・肉体的な負担は大きいのです。
Cランク社員の方々が苦しんでいることをわかっているからこそ、面談者も苦しい――それが現場のリアルです。
まとめ
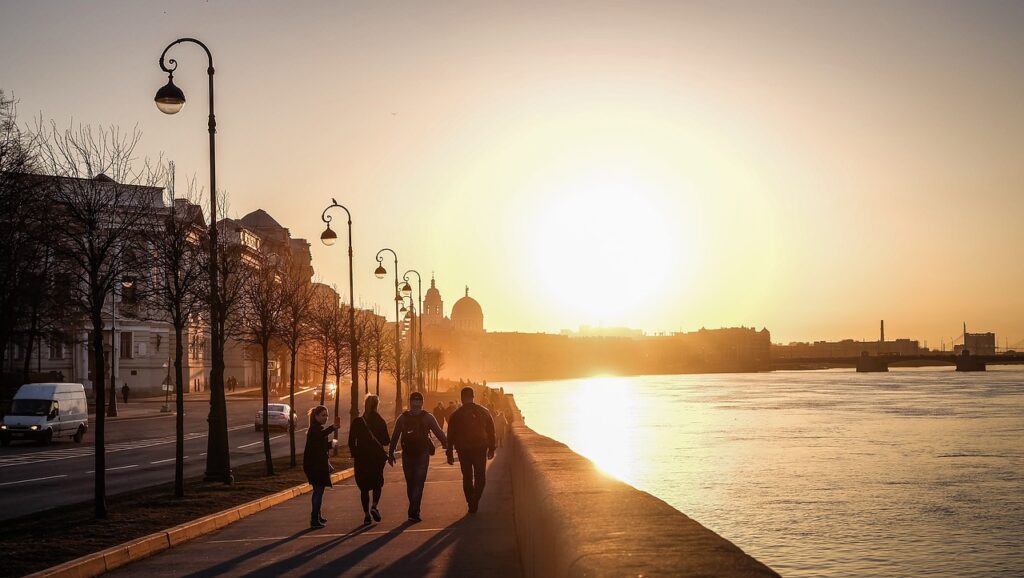
早期・希望退職制度は、企業が経営の方向転換や組織の再構築を図るための重要な手段です。
しかし、その対象となる社員、とくにCランクに位置付けられた方々にとっては、これまでの努力や信頼が報われないように感じられる、非常に厳しい現実でもあります。
もちろん、制度には応募の期限があり、その期限までに応募しなければ「退職しない」という選択も可能です。
断り続ければ、会社に残るという道も形式上は残されています。
しかしながら、会社側はCランクと判断した時点で、「これ以上は戦力として期待していない」というメッセージを発しています。
そのまま会社に残っても、将来的に重要な仕事を任される可能性は低く、評価や環境も決して良くなるとは言えません。
今後もこの会社で働き続けることが、その方にとって本当に幸せな道なのか――多くの方が、その問いと向き合うことになります。
辛い決断ではありますが、だからこそ、この局面を「新しいスタートのきっかけ」に変えていく勇気も大切です。

本当に辞めて大丈夫かな…もう再就職なんて無理かも…

大丈夫ですよ。 あなたのこれまでの経験には価値があります 自信を持って前に進んでいきましょう
過去を否定するのではなく、これまでの経験を活かして、次のキャリアをどう築いていくか。
そのための準備と情報が、きっと力になります。
以下の記事を参考として読んでみてください。
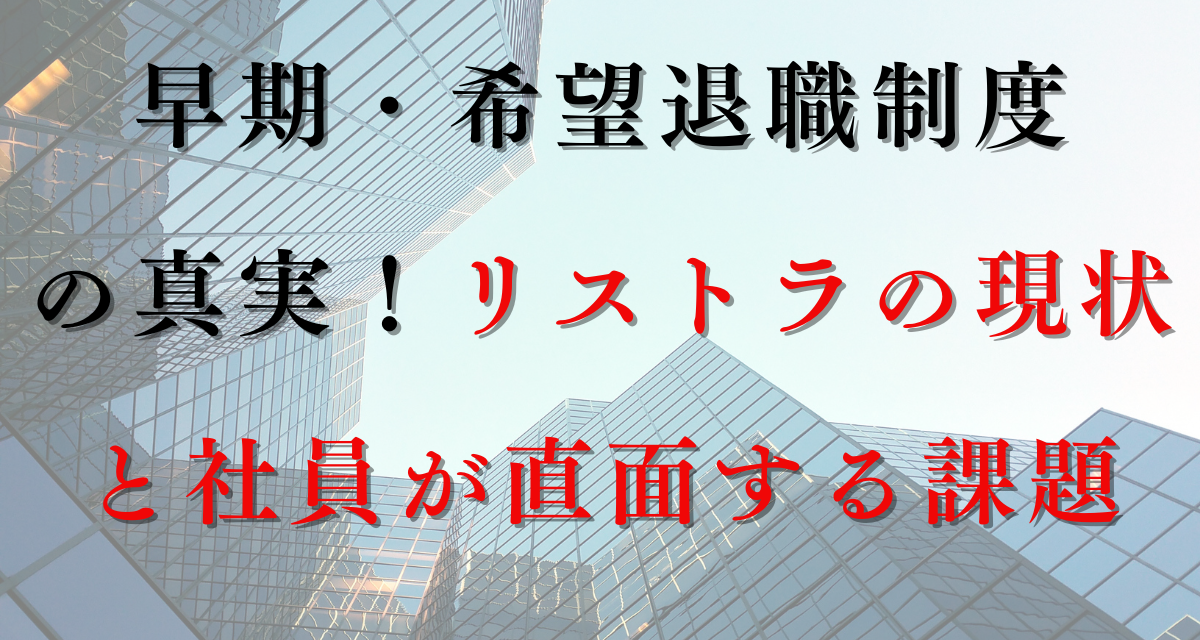


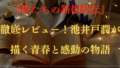
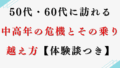
コメント